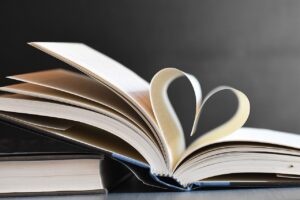【序章】無知だとヤバい…対人援助職がマーケティングを学ぶべき理由
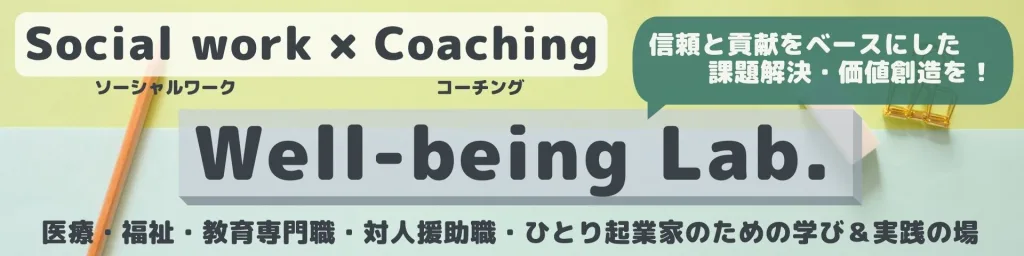

こんにちは!森山です。
今回は
対人援助職がマーケティングを学ぶべき理由
についてお伝えします。
また、今回の記事は
連続講座形式
で、初心者にもわかりやすくご紹介していきますね。

起業初心者
マーケティングって、なんでしたっけ?
聞いたことはありますが…。

はい。基本的なことからわかりやすくお伝えしていきます。
お仕事に活かせたり、人生を充実させ豊かなつながりを育む上でものすごく重要な概念です。
ぜひこの機会に学び取っていただければと思います!
社会福祉士、介護職、看護師、カウンセラー、教員、臨床心理士などの対人援助職。
これら、人の支援や教育などに携わる専門職の方々にとって「マーケティング」という言葉は少し距離を感じるものかもしれません。
マーケティングはどうしても、「営利追求」「売り込み」「競争」といったイメージが先行してしまいます。
私もそうでしたが、ビジネスについて学び始めたときにどうしても心理的な抵抗があり、自分たちの価値観とは相容れないものとして捉えてしまっていました。
しかし、学べば対人援助職にこそ重要な概念ではないかと感じましたし、複雑化する時代を生きる私たちは、今こそマーケティングの本質を理解すべき時が来ていると思うんですね…。
その辺りも含めて、マーケティングの重要性・必要性について解説していきますので、お付き合いいただければと思います。
Contents
社会貢献だけでは続かない現実&想いは届いてる?

多くの対人援助職の方が、
- 「人の役に立ちたい」
- 「社会をより良くしたい」
など、純粋な想いで職業を選択されていることと思います。これまでの経験がきっかけになったり、目指すべき未来を達成する手段として、今の職業を選択されたのでしょうか?どのような理由にせよ、その想いは素晴らしいと思いますし、社会にとって欠かせない価値ある仕事に取り組んでいることに、誇りを持ってもいいと思うんです。
対人援助職のオモイがカタチにならない
でも一方で、現実には組織の制約や予算の限界、人員不足、制度の壁などにより、理想とする支援ができない方も多いのではないでしょうか?
また、長年の経験を積み、専門性を高めてきたにも関わらず、所属組織の枠組みの中では自分の能力を十分に発揮できない…悔しい。そう感じている方も多いのが実情で、私も日々地域で働く対人援助職の方の相談をお受けしたり、オンラインでの想いを伺い、アドバイスさせていただくことも多いです。
自分らしさを活かしてより良いサービス提供を!
想いを持って選んだ仕事だから、目の前の人が困りごとを解消し、幸せな状態になるための貢献がしたい!
そう思うからこそ、
- 「もっと多くの人を支援したい」
- 「自分の経験を活かして新しいアプローチを試したい」
- 「制度の隙間で困っている人たちに手を差し伸べたい」
という想いを抱き、なかなか思うようにいかず焦ったり不安になったりしてしまう…。そんなこともあるようです。
実際、このような状況に直面している方は少なくなく、これまでにたくさんの相談を受け、問題を乗り越えるための伴走サポートも展開してきました。
燃え尽き症候群になる前に
思うようにならない現状を前に、燃え尽き症候群や職業的疲弊感に悩まされる対人援助職も増えていると聞きます。
「自分は誰かの役に本当に立てているのか?」というような不安感。
それだけでなく、給与面での不安、キャリアアップの限界、社会的な評価の低さなど、現実的な問題も無視できない…。純粋な使命感に加え、長期間にわたって質の高い支援を提供し続けることの難しさに打ちのめされてしまう方がいるのも実情です。
支援者としての経験が「価値」になる時代
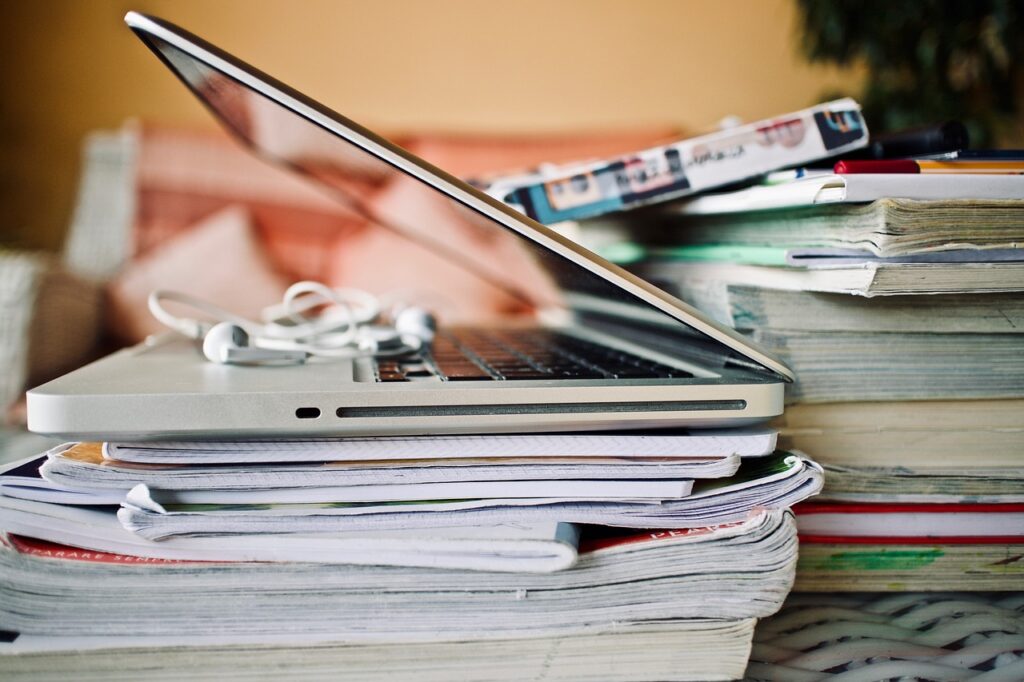
一方で、現代社会にも目を向けるとどうでしょうか?私たちが直面するニーズは急速に多様化し、複雑化する中で混沌としているように感じます。
新しい社会問題や具体的課題が次々と…
少子高齢化、核家族化、地域コミュニティの希薄化、働き方の多様化、メンタルヘルスの課題、発達障害への理解、LGBTQ+への配慮不足やハラスメント、外国人労働者の増加…。これら、従来の制度やサービスだけでは対応しきれない新たな課題が次々と生まれています。法律や制度の整備には時間がかかり、対応が遅れる中で状況が悪化していくこともたくさんあるでしょう。
そこで辛い想いをするのはいつも困難な状況に置かれた「人」です。私も対人援助職としての実践において、「なんとかしたい」けど「八方塞がり」「できることが少ない」と感じることもあります。
対人援助専門職の洞察力が求められている
ただ私たちは、「目の前の人」に対し、専門性と倫理性を持って向き合い、ともに何ができるかを考えるような実践を展開してきたはずです。このような複雑化する社会で、AIやデジタル化がどんどん進む時代だからこそ、実際に「人」と向き合い、様々な課題解決のプロセスを伴走してきた専門職の経験や洞察力が、新たな価値として強く求められているのです。
例えば、現場で培った
- 「人や関係性を見る目」
- 「場や状況を読み取る力」
- 「適切な関わり方について判断する能力」
- 「継続的な関係を築くスキル」
これらはすべて、現代社会が切実に必要としている能力なんですね。
例:対人援助職がニーズを理解し適切な価値を届ける
例えば、子育て支援の経験があり、さまざまな家庭や子育て支援を必要とする方の状況を知っている方が、現場の声を反映する形で制度づくりやサービスづくりに関わることができたらどうでしょうか?働く母親が抱える孤独感や情報過多による混乱を理解し、本当に必要なサポートを提供できるかもしれません。
高齢者支援の経験も同様です。デジタル化が進む社会で取り残されがちな高齢者のニーズを的確に把握し、適切な橋渡し役を果たすことができる可能性はありますよね!
このように、現場のニーズや共通する課題を紐解き、必要なサービスを調整する力(マーケティング力)は、これからの時代に必要とされていることがわかります。
対人援助職の小さな起業=価値提供の新しい形

ここで、少し踏み込んで「働き方」について迫っていきます。
対人援助職の働き方と起業について
「働き方」と一言で言ってもいろんな捉え方があると思います。世代によってその捉え方が違ったり、「雇われて働く」とか「自分で事業を営む」など形態も様々です。ただこの後については、「起業」について取り上げて話をしていこうと思います。とはいえ、「起業」という言葉にあまり反応していただく必要はありません。
「起業」と聞くと、大きなリスクを取って会社を立ち上げ、多額の資金を投入して事業を展開するイメージを持つ方も多いかもしれませんが、ここではもっと小さな一歩も含めて「起業」とします。「できることから取り組み、新たなサービスを作る」とか「自宅で事業や取り組みを立ち上げる」ということなど、一人でできたり今すぐできることも起業…。そんなふうに考えたいという意図があることをご理解ください。
また、実際に「今までにはなかったものを生み出す」「情報収集し、自分で考えて決断する」というような起業家としての思考が、今後の対人援助職には求められることも前提に、読み進めていただければ幸いです。
対人援助職がスモールビジネス・プチ起業を実践
今や働き方と言われると、在宅ワークは当たり前の時代ですよね。コロナ禍でその動きは加速しましたが、オンラインでの価値提供・サービス提供や遠隔での決済システムなども構築されています。そんな中で、スモールビジネスやプチ起業と言われるような価値の生み出し方・届け方がたくさんあるのはご存知ですか?
対人援助職が自宅でパソコン一台で起業できるって?
例えば、「ホームページを作成できる」「グラフィックデザインができる」ということだと、イメージしやすいでしょうか?メールでクライエントとやり取りをして、自宅でパソコンで作業をして、納品することを自宅で完結できる。そこで、住居を構えず旅をするように地方を転々としながらパソコン一台で仕事をするアドレスホッパーと呼ばれるような働き方や、ノマドワーカーと言われるようなカフェなどで働く人が現れるようになったんです。
さらに最近はZoomなどオンラインでセッションや講座などができてしまうので、対人援助職も在宅・オンライン起業ができるんですね。
自分の専門性や経験値を活かして価値を生み出し届ける
では実際に対人援助職が自身の経験値や強み、学びやスキルを活かして起業しようとした時のことを考えてみると、何が必要でしょうか?「自分の専門性や経験を活かして、それを必要としている人に価値を届ける」ために、何をすべきか…。このことと向き合い、考えて、実践を繰り返せるかどうか。そして、実際に顧客に対してアプローチし、ニーズを満たし価値を生み出すことができるかが問われてきます。
私も、副業から始めて教育事業を立ち上げました。その後、コーチングやコンサルティング、オンラインでの相談サービス、専門知識を活かしたセミナーやワークショップの開催、執筆活動による情報発信などを行ってきました。
この時に、対人援助職として積み重ねてきたものが想像を遥かに超えるくらい活用できたという実感があります。
つまり、ビジネス上の価値想像をする時も、社会的に意義がある業務をこなすときも、「ニーズを把握し」「価値を届ける」ということはものすごく重要で、課題解決や価値想像力を高めるための学びを重ねていくことが、今求められる具体的なアクションだと思うんです。
対人援助職としてあなたらしく働き、貢献し、稼ぐ
では起業について考えて具体的に一歩踏み出そうとした時に、「自分にできるのか」「失敗しないのか」ということが不安になることもあるかもしれません。
そこで、「自分らしさを失う」「焦りが積み重なって行動できなくなる」ということになるかもしれませんが、それは完全にNGです。
なぜなら、起業家にとっては「自分で考えて決断する力」が非常に重要で、「決断できない」「迷う」ということが命取りになるからです。
小さく一歩を踏み出しコツコツ育てていく
そこで実践上のポイントは小さく始めることです。あなたが起業を志すとき、おそらく初期段階で重要なのは大きな事業を急いで立ち上げて社会にインパクトを残すことではなく、リスクをコントロールしながら堅実に価値の循環を起こすことではないかと思うんですね。
ここで「リスクをコントロールしよう」「堅実な戦略を取ろう」と思うと、小さなアクションを積み重ねていくことが大事です。
テストと改善を繰り返しながら、あなたの想いを形にできるような事業が展開できるかや、人生や大切な人との生活が幸せで豊かなものになるかを確かめつつ方向性を見定めていけるといいですね!
起業家として目指す状態を常に意識し小さな一歩から踏み出す
そこで重要なのが「マーケティング」です。誰に対して何を届け、どんなふうにアプローチしていくかを考えていくこと。このようなリサーチとか分析とか、テストと改善を繰り返せる対人援助職・起業家は「本当に困っている人に、その人が求める価値を適切な形で提供できる」という状況を生み出せます。
「起業塾に通えば稼げるって聞いた」「認定資格を取ると集客に苦労しないと思っていた」という勘違いをして、どうしようもなくなって私のもとに相談に訪れられる方がおられます。
実際は「あなたにどんな強みがあるのか」「何からすればいいのか」「どうすればより大きな価値をたくさんの人に届けられるのか」ということを練り上げていくことが大事です。
また、対人援助職…つまりコーチングやカウセリング、コンサルテーションや講師業などを展開するということですので、「目の前の人が何を求めているかということを理解・把握するためのアクション・意識・姿勢」は持ち続ける必要があります。
目先の結果やお金のことに囚われて、本当に重要なことを忘れてはいけないということは、「雇われて働く」ことを考えてもそうですし「小さく起業する」時にも忘れてはいけません。
収入を安定させ自分を成長させ価値を増大させる循環を
ではもし雇われて働きながら、副業として事業をスタートさせ、月に数万円の売上であったとします。すると、そのお金を使って更なる学びを重ねることができます。また、学びを重ねてより大きな価値を生み出せるようになると時間的・経済的・精神的余裕が生まれます。価値を生み出し届けて収益を得て、その収益を自己投資に充てて、ますます大きな価値を生み出し届けられるようになるという好循環を生み出す意識を持てれば、高いモチベーションを保って学びと実践を続け成長と成果を掴むことができますよ!
価値を生み出し届ける事業を小さく生み出しコツコツ育む
ここまでお伝えしたように「自分に何ができるのか」や「お客さんは誰で、その人は何を求めているのか」ということを把握するよう努め、お客様にとって価値があり、自分自身も価値提供を通じて成長できる事業を構築できれば、働くことの意味が根本的に変わる可能性があります。
私は今、起業家としても、まちづくりなどの活動実践者としても、対人援助職としても活動をしています。どのような実践においても、マーケティングについて学ぶことは非常に重要な意義があったなぁと思うので、今回はまず「マーケティングが重要であり学ぶべき理由」についてみていきました。
マーケティングについて、より具体的で踏み込んだ実践的な内容は次回以降の記事で情報提供していきますね!
【2月限定/先着10名のプレゼントを公開中】
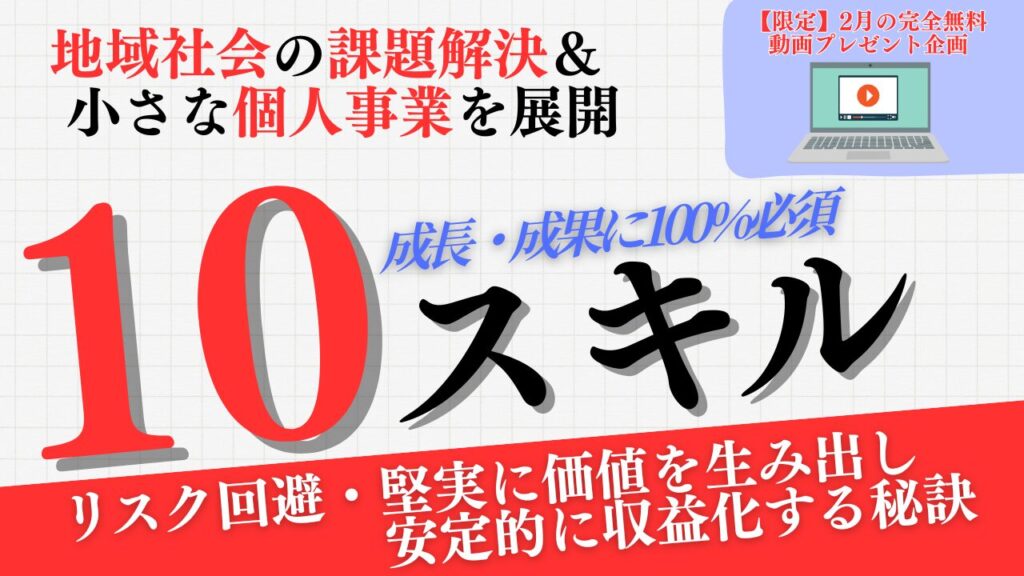
無料で基本から学べる動画を10本お届け!
1本あたり5分ほどでサクッと学ぶことができます。
いつでもどこでも学べる貢献型ひとり起業のノウハウ
自宅でもカフェでも通勤電車の車内でも、ネットがつながる環境ならしっかり学べます!
会員サイトには、その他「起業」「収益化」「価値創造」「貢献」「自己管理」「習慣改善」「学習効率化」など多数のコンテンツを公開しています。
一部ダウンロード可能なコンテンツもありますので、聞き流しながらマインドセットを固めスキルを高めることができます。
さらに!早期申込特典アリあとわずか!
期間・人数を限定してお届けしています。
(リンクが切れている場合は申込終了となっています。ご了承ください)
⚠️注意:こんな人はすぐに登録を解除します。
「誰かの役に立ちたい」「自分らしさを活かした仕事がしたい」「大切なものを守るために解決したい問題や課題がある」という方を対象とした学びの場ですので、「お金が儲かればなんでもいい」という方はお断りです。
「ノウハウだけが欲しい」
「学びや実践をする気はないけど、ちょっと内容が知りたい」
という方は、成長もしませんし、成果も出ません。
次のような方は今すぐご登録ください。
もし、
- 「目の前の人の役に立ち、社会で自分の役割を果たす」
- 「安定的な収益化と健全な資金繰りで事業を成長させたい」
- 「自分自身の健康や大切な人との時間を守りたい」
という想いをお持ちなら、「想いを言葉にする」「小さく実践をする」ということを繰り返しながら、「共感」をベースに事業を成長させていきましょう。
私も全力で、提供できる限りの情報をお届けしていきます。