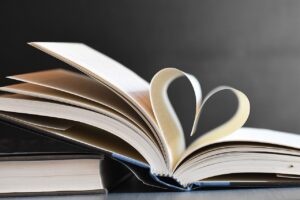【第2章】マーケティングで対人援助職の得意を10倍化し社会貢献×収益化
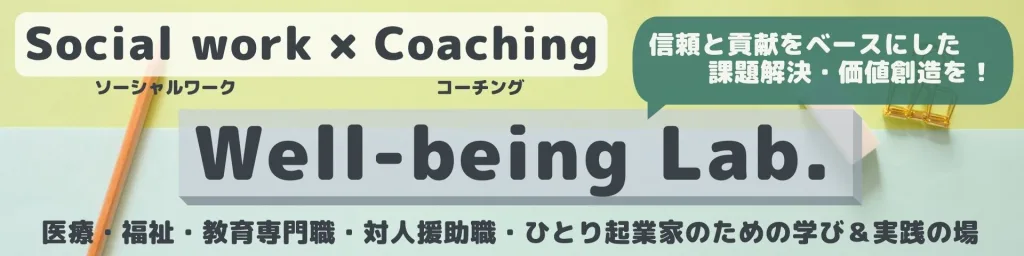

こんにちは!森山です。
今回は
マーケティングについて学び、仕事で生み出す価値を10倍化する方法
についてお伝えします。
また、
マーケティングの「マ」の字もわからない
という方にも、わかりやすく情報提供していきますね!

とはいえ、ビジネスとかお金の話とか、難しいことは本当に全然分かりませんよ!
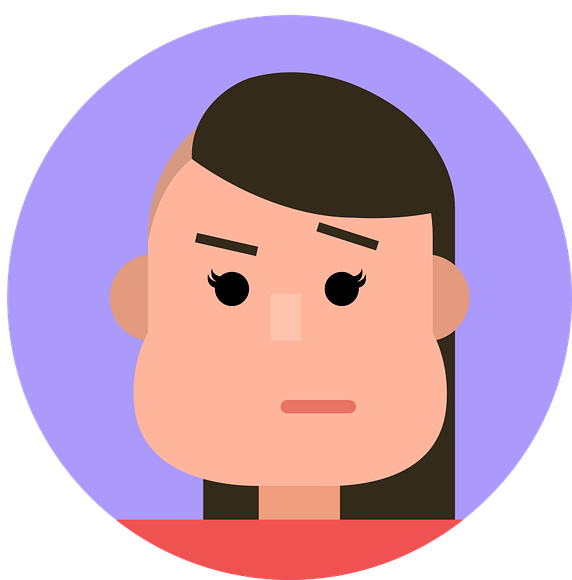
私もです。これまで雇われて働くことしかしたことないですし…。

はい、そんな方にこそご覧いただきたい内容を今回はお届けしていきますね。
今回はマーケティングの超基本と、自分の具体的なアクションで届けたい価値を10倍化して届ける方法についてみていきます。
その中で、マーケティングに関する誤解が解けるかもしれませんし、魅力を感じるかもしれません。
これからの複雑で変化の激しい時代に、自分の価値を最大化し、相手の抱えている問題を解決する方法を学んでおくことの重要度は高くなる一方だからです。
ぜひ、一緒に見ていきましょう!
Contents
マーケティングは「人を見る力」に通じる

マーケティングを超簡単に説明するなら「売れる仕組みづくり」です。
その本質は、相手(ターゲット)を深く理解することにあります。
価値を生み出し届けるためには「相手」を理解する
売れる仕組みづくりについて考えたときに、「誰が」「何を」欲しているのかを理解すること。そして、ピンポイントで望むものを提供できれば価値提供に成功するわけです。
- 「この人は何に困っているのか」
- 「どんな背景や事情があるのか」
- 「どのような状況に置かれているのか」
- 「どのような支援や解決策を求めているのか」
- 「どんな価値観を持っているのか」
これらを正確に把握することこそ、マーケティングにおける情報収集でものすごく大事!
ただこれらって、対人援助職が長年にわたって培ってきた専門技術そのものではないでしょうか?
ソーシャルワーカーのアセスメント
例えば、ソーシャルワーカーは実際の介入の前に「アセスメント(情報収集・分析)」をします。
いきなり思いつきで支援を展開するのではなくて、クライアントの表面的な問題の背後にある真の課題を見抜き、支援や介入の方向性を見定めるんですね。
こうすることで、事態が悪化するのを防いだり、より質の高いサービスを提供したりできるようになります。
つまり、アセスメントするからこそ、クライエントの生活の質を高めるような実践が展開できるんですね。
社会の中で生きづらさを抱える方へのサービス提供
対人援助職としてなんらかの生きづらさを抱えた「人」を相手にすることを考えた時、その人の物理的・精神的情報をしっかりと受け止めながら一緒に整理を試みます。
経済的困窮を訴える人の背景に精神的な不調があったり、子どもの問題行動の原因が家庭環境にあったり、高齢者の身体的不調の裏に社会的孤立があったりする…。
この複雑な状況を少しずつ紐解いていくんですね。
多層的で複合的な課題を理解→マーケティングとの親和性
多層的で複合的な課題を理解し、適切な支援方針を立てる能力は対人援助職であれば学びと実践を通じて高めてきたはずです。
これは「ビジネスにおける価値提供」において非常に有効です。
マーケティングにおいて「真のニーズを見抜く力」は非常に重要な価値を持ちます。
表面的な要望ではなく、お客様が本当に求めているものを理解できる人は、ビジネス・マーケティングの世界でも高く評価されるんです。
クライアント支援と共通する「観察力・傾聴力」

ソーシャルワークやカウンセリングにおけるアセスメントでは、クライアントの言葉だけでなく、表情、声のトーン、身振り手振り、服装、姿勢、さらには語られない部分、沈黙の意味にも注意を向けます。
この多角的で繊細な観察力と傾聴力は、市場やお客様のニーズを理解する上でも極めて有効です。
観察力と洞察力を起業や人間関係構築に活かす
例えば、
- 面談の際に「大丈夫です」と言いながらも表情が曇っているクライアントに気づく力はありますか?
- 言葉では強がっているけど、実は不安を抱えていることを察知する感受性はありますか?
- 相手が本当に言いたいことを引き出すコミュニケーション技術を持っていますか?
これらはすべて、お客様の真のニーズを理解し、適切なサービスを提供するために不可欠な能力なんですね。
信頼関係構築の重要性を理解→コツコツ積み重ねる
また、対人援助職は「待つ」ことの大切さも知っています。
- 相手が話したくなるまで待つ
- 相手のペースに合わせる
- 急かさずに相手の準備が整うのを待つ
このような姿勢は、ビジネスにおけるお客様との信頼関係を築く上でも非常に重要だと私は考えています。
逆に無理に相手を動かそうとすると、対人援助実践もビジネスもうまくいきません。
関係性が崩壊し、クライエントさんを大きく傷つけてしまうこともあるので、最新の注意が必要であり、誠実な姿勢を持ちつづける意識が最重要です。
あなたのサービスを必要としている人の探し方
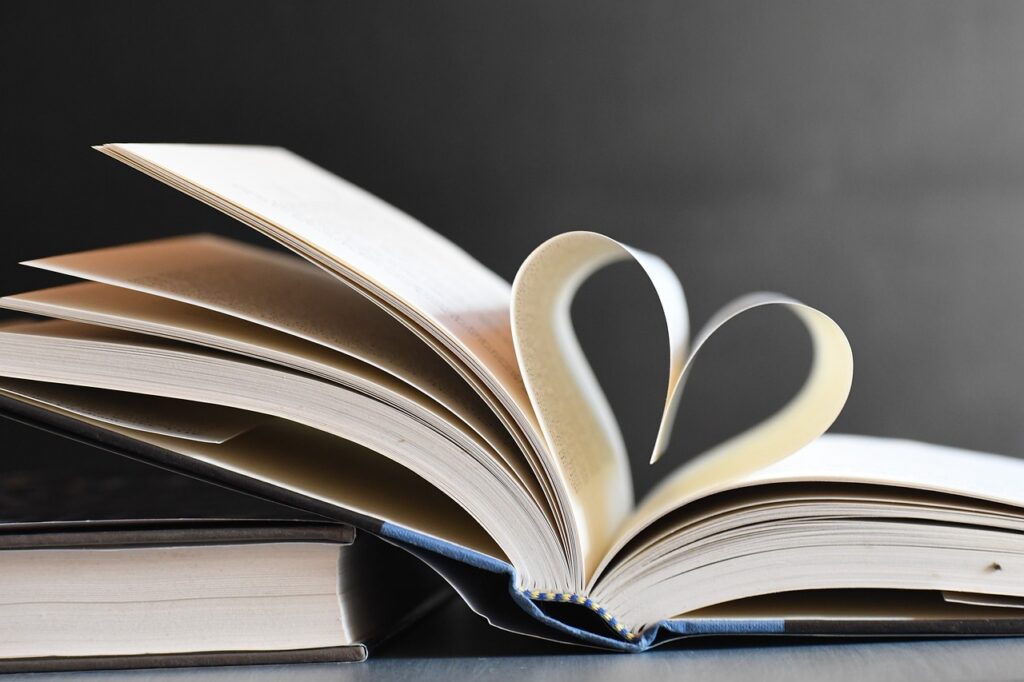
マーケティングにおいて重要なのが「ターゲット設定」です。
これも、支援職にとっては馴染みのある考え方ではないでしょうか?
ソーシャルワーカーとして「人」に対して支援・介入する
ソーシャルワーカーが介入する対象は「組織」「地域」などの様々なシステムですが、必ず「クライエント(人)」の存在を意識することが大事です。
どのような背景を持つ人が、どんな課題を抱え、どのような支援を求めているかに向き合うところから始めます。
ビジネスの場合も目の前のお客さん一人一人にしっかり向き合うことが大事だと言うのが私の考え方ですし、これからビジネスを展開する人は、まずお客さんにしたい人を具体的にイメージすることから始めるのがいいですね!
社会資源開発における考え方=マーケティング
では、「たった一人の人(ターゲット)」を思い浮かべてみましょう。
過去に関わったクライアントの中で想定していただいても構いません。
そこで、
- 「もっとこんなサービスがあったらよかったのに」
- 「制度の隙間で困っている人がいる」
- 「既存のサービスでは対応しきれない課題がある」
と感じた経験はありませんか?
その経験こそが、新たなサービスのヒントになるのです。
例:子育て支援の経験や高齢者支援の経験(生の声)などが大事
例えば、子育て支援の経験があるなら、
- 「忙しい母親が本当に求めているのは育児情報ではなく、話を聞いてもらえる場所かもしれない」
- 「父親向けの育児支援が不足している」
- 「きょうだい児への配慮が足りない」
といった深い洞察ができるはずです。
高齢者支援の経験があれば、
- 「認知症の初期段階での相談先が少ない」
- 「家族介護者への支援が不十分」
- 「地域での見守り体制に課題がある」
といった問題意識を持っているでしょう。
問題意識を価値提供のアイデアに変える
これらの問題意識は、そのまま新しいサービスのアイデアになります。
そして、そのような課題を抱えている人がどこにいるのか、どのような方法でアプローチすればよいのかも、現場経験があるからこそ分かるわけですね!
では、続いて第3章では、洞察力についてみていきますね。
【2月限定/先着10名のプレゼントを公開中】
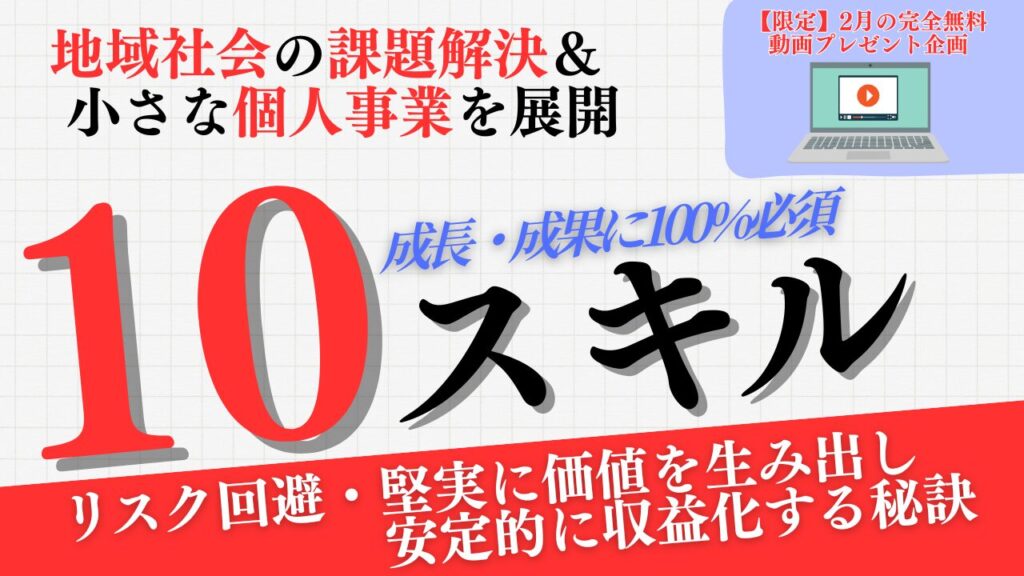
無料で基本から学べる動画を10本お届け!
1本あたり5分ほどでサクッと学ぶことができます。
いつでもどこでも学べる貢献型ひとり起業のノウハウ
自宅でもカフェでも通勤電車の車内でも、ネットがつながる環境ならしっかり学べます!
会員サイトには、その他「起業」「収益化」「価値創造」「貢献」「自己管理」「習慣改善」「学習効率化」など多数のコンテンツを公開しています。
一部ダウンロード可能なコンテンツもありますので、聞き流しながらマインドセットを固めスキルを高めることができます。
さらに!早期申込特典アリあとわずか!
期間・人数を限定してお届けしています。
(リンクが切れている場合は申込終了となっています。ご了承ください)
⚠️注意:こんな人はすぐに登録を解除します。
「誰かの役に立ちたい」「自分らしさを活かした仕事がしたい」「大切なものを守るために解決したい問題や課題がある」という方を対象とした学びの場ですので、「お金が儲かればなんでもいい」という方はお断りです。
「ノウハウだけが欲しい」
「学びや実践をする気はないけど、ちょっと内容が知りたい」
という方は、成長もしませんし、成果も出ません。
次のような方は今すぐご登録ください。
もし、
- 「目の前の人の役に立ち、社会で自分の役割を果たす」
- 「安定的な収益化と健全な資金繰りで事業を成長させたい」
- 「自分自身の健康や大切な人との時間を守りたい」
という想いをお持ちなら、「想いを言葉にする」「小さく実践をする」ということを繰り返しながら、「共感」をベースに事業を成長させていきましょう。
私も全力で、提供できる限りの情報をお届けしていきます。