【第3章】対人援助職・起業家の土台&価値を100%確実にする鍵とは?
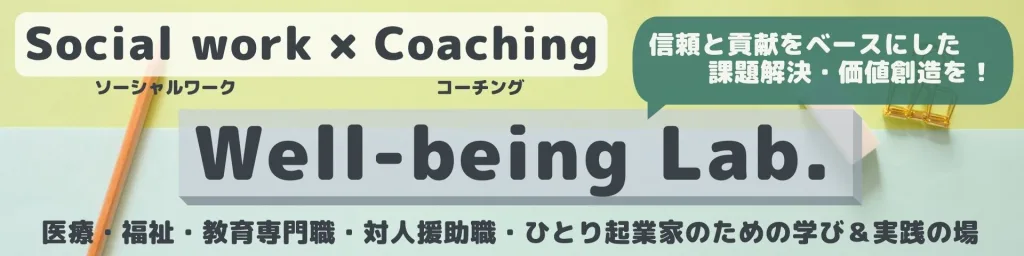

こんにちは!森山です。
今回は
対人援助職が起業を考えて実際に行動した際に「ここを見逃したら100%失敗する」という概念
についてお伝えします。
また、
「失敗」を回避し、「困難」を乗り越えるためにめちゃくちゃ重要な概念
についてもわかりやすくご紹介していきますね。

実際、起業しているんですが、全くうまくいきません。
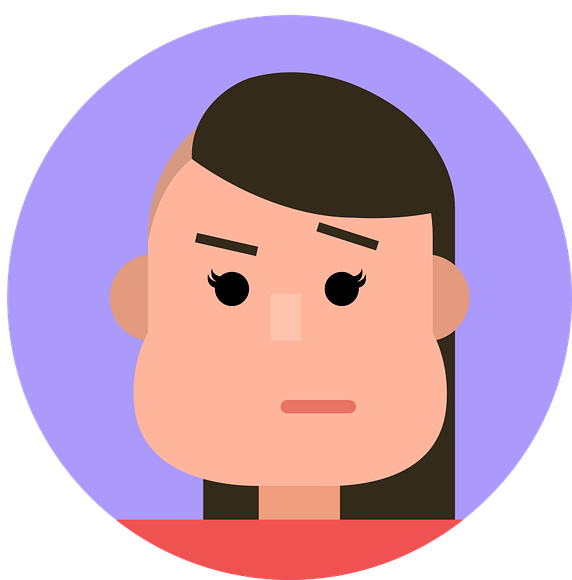
私は看護師としてのキャリアを活かして、これから起業しようと思っているんだけど…

どちらも場合も、今回の記事の内容はぜひチェックしてみてください!
ビジネスは問題解決であり、価値と価値の交換です。
お客さんが抱えている問題に対して、自分の強みを活かして価値を届けること。
その際、表面上の問題ではなくて、本当の問題にアプローチすること。
そのために、じっくり観察し、対話し、共感を持って状況を理解し、時に一緒に考えながら、「何を」「どのようにするのか」を考えること。
このような「洞察」こそが非常に重要なんです。
これができる力があるかないかでは天と地ほどの差があります。
「何をどうすべきかわからない」「どう頑張ったって価値を届けられない」ということなのであれば、もしかすると「洞察」に伸び代があるような気がします。
そこで、今回は「洞察」についてみていきますね。
Contents
「この人は何に困っているのか?」を掘り下げる力

対人援助職は、日常的に
- 「なぜこの問題が起きているのか」
- 「根本的な原因は何か」
- 「表面的な問題の背後にある真の課題は何か」
を考える習慣があります。
この問題の本質を見抜く力、課題の構造を理解する力は、ビジネスにおいても極めて重要です。
気づく力は対人援助職が最も重要視して磨いてきた力
例えば、介護の現場で働いている方なら、「利用者の問題行動」の背景には、身体的な不調、認知機能の低下、環境の変化への不安、コミュニケーション不足、過去のトラウマなど、様々な要因が複合的に関わっていることを理解しているでしょう。
この多角的な視点と分析能力は、お客様の課題を深く理解し、根本的な解決策を提案する上で非常に価値があります。
価値提供は「気づき」と「深掘り」から始まる
市場に出回っている多くのサービスは、表面的な問題に対する対症療法的な解決策にとどまっていることが少なくありません。しかし、真の課題に向き合い、根本的な解決を目指すサービスを提供できるからこそ、お客様から深く信頼され、継続的に選ばれ続けるのです。
データよりも目の前の「声」を聴く大切さ

現代のマーケティングというとビッグデータやAI分析を重視する傾向があります。ただ、対人援助職の小さな起業における真の強みは「一人ひとりの生の声」に耳を傾けられることです。
統計では見えない個別のニーズや感情、その人特有の事情や背景を汲み取る能力は、他の業界の人には真似できない貴重なスキルです。
ひとりのクライエントと向き合うこと
一人のクライアントから得た深い洞察が、実は多くの人が抱える共通の課題を浮き彫りにすることは珍しくありません。
「この人だけの特殊な問題だ」と思っていたことが、実は社会全体の課題であったり、制度の不備によるものであったりすることがあります。
言葉にならない想いを汲み取ること
また、数字やデータでは表現できない微妙なニュアンス、言葉にならない想い、文化的背景や価値観の違いなどを理解できる能力は、グローバル化が進む現代社会において非常に重要です。多様性を理解し、一人ひとりに適したアプローチを考える力は、これからのビジネスにおいて必須の能力となる。
私はそう考えています。
洞察力がある人ほどリピートされる理由

お客様が本当に求めているものを理解し、それに的確に応える提案ができる人は、自然とリピートされます。これは支援の現場でも全く同じです。表面的な対応ではなく、相手の状況や想いを深く理解した上での関わりこそが、真の信頼関係と最高のサービス提供を生み出すのです。
相談者の言葉の背景にある本当の気持ちを理解できるか?
例えば、同じ相談内容でも、経験豊富な支援者とそうでない人では、対応の深さが全く異なります。経験豊富な人は、相談者の言葉の背後にある本当の気持ちを理解し、その人にとって最も適切なタイミングで、最も効果的な支援を提供することができます。
表面的な要望を受けてサクッと処理=完全にNG
ビジネスにおいても同様で、お客様の表面的な要望だけでなく、その背景にある真のニーズを理解し、お客様が気づいていない潜在的な課題まで含めて解決策を提案できる人は、高い評価を得ることができます。このような深い理解に基づくサービス提供は、お客様にとって「なくてはならない存在」となり、長期的な信頼関係につながります。
洞察力を鍛えてひとり起業して価値提供する方法
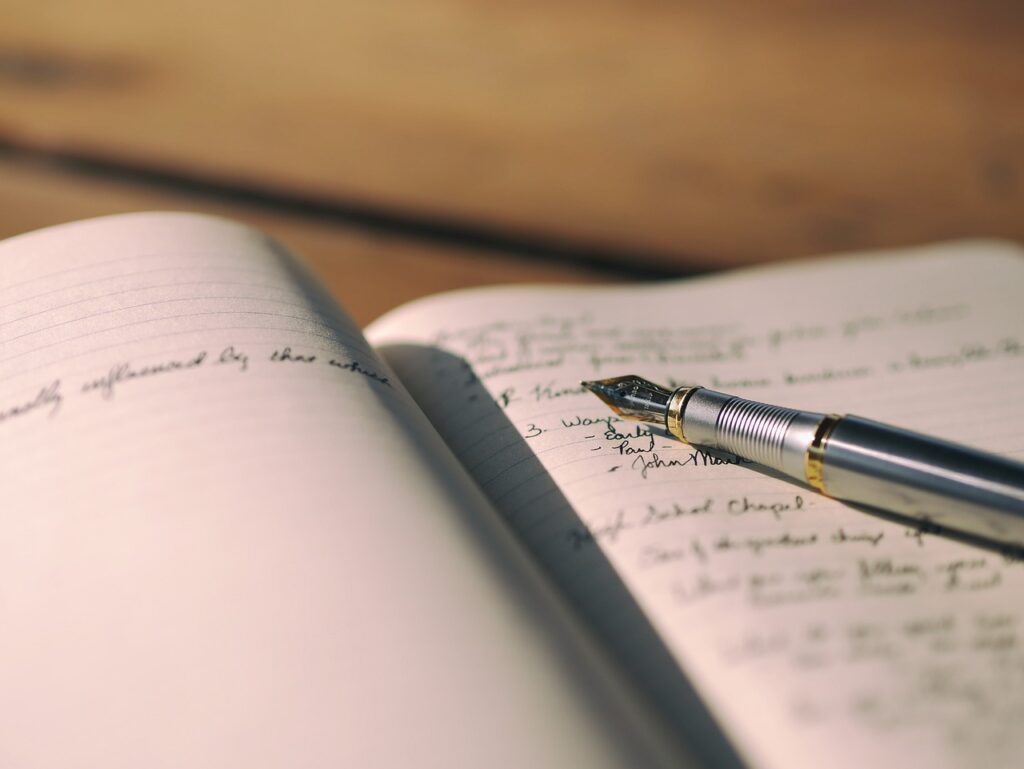
では、対人援助職として起業したり、地域課題の解決や社会貢献を継続した取り組みに変える方法についてみていくときに、どうやって洞察力を鍛えたらいいのか…。
その答えは「シンプルではない」です。
複雑な状況下で100%確実に成長する方法などない。
そんな時の戦略としては、「学びと実践を重ねること」であり、「リスクをコントロールしながらできることにフォーカスすること」です。
学びと実践を重ねて、挑戦をしながら失敗もして、そしてその失敗を振り返りながら学びに変えて、次の実践を繰り返していくこと。
この「学びと実践の繰り返し」については、第4章でみていきますので、ぜひチェックしてみてください。
【2月限定/先着10名のプレゼントを公開中】
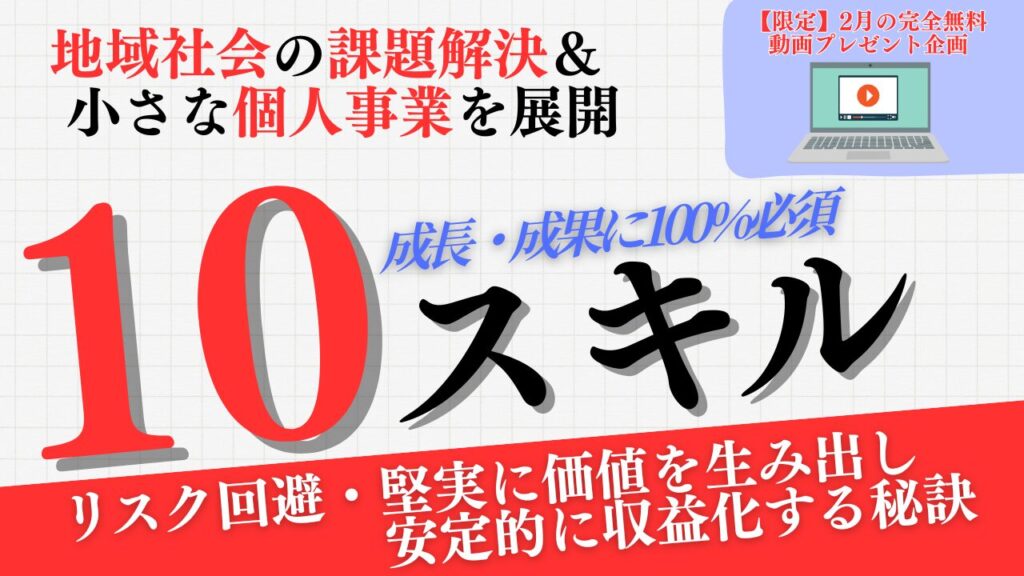
無料で基本から学べる動画を10本お届け!
1本あたり5分ほどでサクッと学ぶことができます。
いつでもどこでも学べる貢献型ひとり起業のノウハウ
自宅でもカフェでも通勤電車の車内でも、ネットがつながる環境ならしっかり学べます!
会員サイトには、その他「起業」「収益化」「価値創造」「貢献」「自己管理」「習慣改善」「学習効率化」など多数のコンテンツを公開しています。
一部ダウンロード可能なコンテンツもありますので、聞き流しながらマインドセットを固めスキルを高めることができます。
さらに!早期申込特典アリあとわずか!
期間・人数を限定してお届けしています。
(リンクが切れている場合は申込終了となっています。ご了承ください)
⚠️注意:こんな人はすぐに登録を解除します。
「誰かの役に立ちたい」「自分らしさを活かした仕事がしたい」「大切なものを守るために解決したい問題や課題がある」という方を対象とした学びの場ですので、「お金が儲かればなんでもいい」という方はお断りです。
「ノウハウだけが欲しい」
「学びや実践をする気はないけど、ちょっと内容が知りたい」
という方は、成長もしませんし、成果も出ません。
次のような方は今すぐご登録ください。
もし、
- 「目の前の人の役に立ち、社会で自分の役割を果たす」
- 「安定的な収益化と健全な資金繰りで事業を成長させたい」
- 「自分自身の健康や大切な人との時間を守りたい」
という想いをお持ちなら、「想いを言葉にする」「小さく実践をする」ということを繰り返しながら、「共感」をベースに事業を成長させていきましょう。
私も全力で、提供できる限りの情報をお届けしていきます。


