社会福祉士が5つのステップで最高のキャリアを実現〜体験日記〜
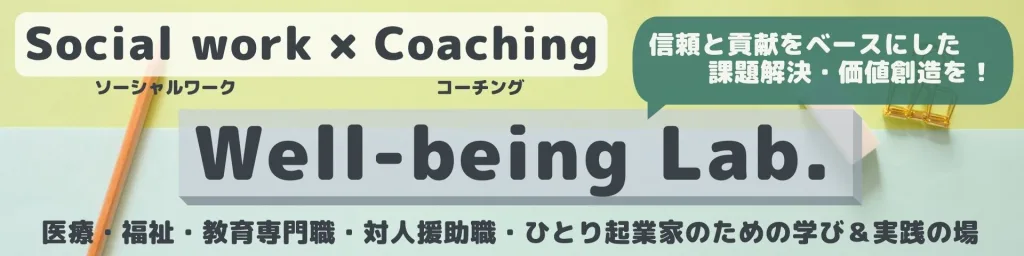

こんにちは、森山です。
社会福祉士の国家資格を取得するために、長い勉強期間を費やした…。
でも、資格を取得後、現場では「これからどうすればいいのか」「このまま本当に自分はやっていけるのか」と不安を感じてしまう…。
そんなことってないでしょうか?
実は、多くの社会福祉士が同じような悩みを抱えています。社会福祉士にとって資格はあくまでもスタート地点に過ぎません。
ただ、その後の学びの機会として、なかなか充実した場がない…。
そんなふうに私は感じています。
本当に大切なのは、学び続ける姿勢を持ち、資格をどう活かし、どのように実践していくかということのはず!
そこでこの記事では、「単なる資格保持者」から、「社会に真の貢献ができる社会福祉士」へと成長するために、私が実践してきた道であり、具体的な提案も織り交ぜつつを共有したいと思います。(私も実践中の身です。共に学び、共に実践し、共に成長を遂げていきましょう)
Contents
「自分らしさ」を発掘〜あなたはどんな社会福祉士?〜
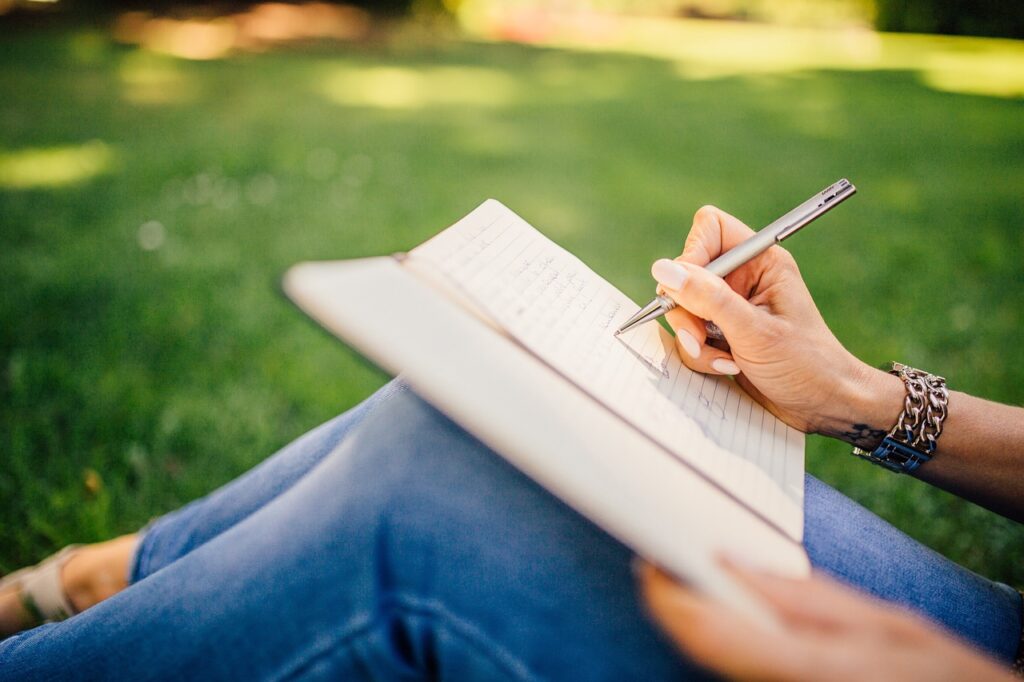
社会福祉士として働き始めると、専門的な知識やスキルが求められます。
しかし、それだけでは十分ではありません。クライエントとの関係性において最も重要なのは、あなた自身の「人間性」や「個性」のように感じるんです。
社会福祉士として自己覚知が大事
まずは自分自身を深く知ること。社会福祉士になるまでのプロセスで「自己覚知」の重要性は習ったはずです。それをまさに実践することがポイントですね。
- あなたはなぜ社会福祉士になろうと思ったのでしょうか?
- どんな経験が、この道を選ぶきっかけになったのでしょうか?
- あなたの強みは何で、どんな価値観を大切にしていますか?
これらの問いに向き合うことで、あなたならではの支援スタイルの土台が見えてくることがあるかと思います。
基本に沿って実践することと自分で考えること
教科書で学んだことは大事ですが、ただ得た知識をその通りに実践しようとするだけではいい支援はできないと思います。
そこで、「自分を知り」「目の前のクライエントを知り」「クライエントを取り巻く環境を知り」「社会を知り」「介入方法を知り」…
ということができているからこそ、いい支援が実践できると思うんです。
まずはその一歩として、自己覚知を意識しながら、基本に忠実な実践をすることが大事だと思うんですよね。
社会福祉士が現場で本当に求められる大切なもの

先ほどお伝えしたように、教科書で学んだ知識は確かに重要だと思うんです。
しかし、現場では教科書には載っていない実践的なスキルや臨機応変な判断が求められます。
社会福祉士としてクライエントとの信頼構築は最重要
特に重要なのが、クライエントとの信頼関係を構築するコミュニケーション力です。
相手の話を丁寧に聴き、共感し、その人の尊厳を守りながら支援する姿勢が何よりも大切だということは、教科書に書いてあるだけではなく、実践の中からも感じます。
自分の役割を深く理解&状況に応じてプロとして仕事をする
また、医師や看護師、ケアマネジャーなど多職種と連携する場面では、社会福祉士としての専門性を発揮しながら、チームの一員として貢献する役割が求められます。
目の前の相手に応じて、もしくは状況に応じて、必要な役割を自分で判断して行うことが大事です。
セルフケアも重要!社会福祉士として燃え尽きないように
そして忘れてはならないのが、セルフケアの重要性です。
人の悩みや痛みに寄り添う仕事だからこそ、自分自身のメンタルヘルスを守ることが不可欠です。
燃え尽き症候群を防ぐためにも、自分なりのストレス解消法や休息の取り方を確立しておきましょう。
社会福祉士の専門性を磨く5つのステップ

続いて、社会福祉士としての専門性を磨く5つのステップについて見ていきましょう。
ステップ1:興味のある分野や領域を見つける
社会福祉士の活躍の場は多岐にわたります。
高齢者支援、児童福祉、障がい者支援、医療ソーシャルワーク、地域福祉など、まずはどの分野に興味があるのかを明確にしましょう。
もちろん、分野に捉われることなく、さまざまな職場・領域について「関心」「興味」が持てることにトライしてみることが大事だと思います。
というのも、「違和感を感じること」「深く実践して見たいこと」などを素直に受け止めることで、頭だけではなく深いレベルで関心がある分野を見つけることにつながります。
ステップ2:現場経験を積みながら学び続ける
現場での経験は、何よりの学びになります。
もちろん、知識を得ることは社会福祉士にとってものすごく大事ですが、実際にクライエントさんと話をして、自分にできることを考えることこそ最大の学びになります。
同時に、研修や勉強会に参加して継続的に知識をアップデートしていくことも重要だと思います。
その際、「自分にとって意味がある学び」と「そうでない学び」をしっかり整理し、受動的ではなく能動的・積極的に学びと実践を重ねることが大事だと思いますよ。
ステップ3:コーチ・メンターや人脈・ネットワーク構築
社会福祉士の専門性を磨く上で、先輩社会福祉士や同じ志を持つ仲間とのつながりを育むことは大事です。
人脈やネットワークは、あなたの成長を加速させることにつながります。
この時も「自分がどうしたいのか」「どんな人とのつながりを欲しているのか」という軸があるからこそ、素敵な出会いが訪れて、ご縁を引き寄せることができる。
一方で、「飲み会に参加する」「ダラダラと一緒に過ごす」ということをしていても、あなたの専門性が高まるわけではありません。
また、メンターやコーチなど、困った時に相談できる人との関係性を築いておくことも大事ですね。
ステップ4:実践を振り返り、言語化する
社会福祉士の専門性の向上において重要なのが「内省」です。
日々の実践を振り返り、何がうまくいったのか、何が課題だったのかを言語化する習慣をつけることをオススメします。
「うまくいった」「ダメだった」ということに一喜一憂する必要はありません。
現実・事実と向き合いつつも、自分が理想とする支援者像をしっかりと胸に抱き、次に何ができるかを考えて自分自身を進化させ、向上させること。
まずこの意識と習慣を構築することが、専門性の向上には必須だと考えます。
ステップ5:独自の支援スタイルを確立し発信する
社会福祉士としての学びと実践を重ね、一定の経験を積むことで「自分のスタイル」が確立できるようになってきます。
また、社会の中で求められる役割なども考えた上で「自分が仕事としてやるべきこと」を見い出せることにつなげられたら、ぜひ次のチャレンジをしていただきたいんです。
小さくてもいいので副業をしてみるとか、自分の実践への想いについて情報発信してみるなどして、共感の輪を広げていってみるのはいかがでしょうか?
すると、さらなる成長と社会への貢献に繋がります。
社会福祉士としての多様なキャリアと無限の可能性

次に、社会福祉士の多様なキャリアとこれからの無限の可能性についても見ていきましょう。
社会福祉士にはいろんな職場・可能性が溢れている
社会福祉士は、一つの職場に留まるものではありません。
行政機関、医療機関、福祉施設、NPO法人など、様々な場所で活躍できます。
また、常勤・正規雇用としての働き方だけでなく、非常勤・パートとしての働き方などもあります。
社会福祉士としての独立開業や副業・副業などの働き方も
近年では、独立開業や副業・複業という新しい働き方も注目されています。
それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあります。
- 安定性を求めるなら行政や大規模な医療機関
- 現場でのダイレクトな支援を重視するなら福祉施設やNPO
- 自分のビジョンを実現したいなら起業
などなど、いろんな選択肢もあります。
大切なのは、社会が激変する時代において、固定的な価値観にとらわれず、これからの自分の価値観やライフスタイルに合った働き方を見つけることだと思います。
社会に貢献し続けるソーシャルワーカーとして

ソーシャルワーカーは、クライエントの生活課題を解消し、Well-beingを高めるために働きます。
そんな私たちの「実践方法」や「社会貢献」の形はそれぞれです。
一人のクライエントに深く寄り添うことも立派な貢献ですし、制度や仕組みを変えていく活動も重要な貢献です。
失敗することを恐れるよりできることを一歩一歩
こんなことを言うと「失敗できない」「しっかりしないと」と思ってしまいそうですよね。
でも、今から全ての実践において完璧を目指す必要はないと思います。
小さな一歩から始めて、継続的に学び、成長していく姿勢こそが大切だと思っています。
可能性を信じて現状を変えていく社会福祉士に
あなたの実践が、誰かにとっての希望の光になる…。
それは事実だと持っています。
自分の可能性を信じ、目指すべき方向性に向けてやるべきことを整理し、一歩一歩前に進んでいく。
それが、あなたが望む結果と成長につながり、クライエントの笑顔や社会の豊かさに変えていけるといいですね!
社会福祉士が5つのステップで最高のキャリアを実現 まとめ

社会福祉士という資格は、私にとって実践をする上での「在り方」のように思っています。
その資格をどう使い、どんな価値を生み出していくかは、自分次第…。
つまり、この記事を読んでくださったあなたが何をどう捉え、今後どうするのかという選択次第なのです。
断言できることとしては、資格取得はゴールではなく、スタートです。
これから始まるあなたらしい社会福祉士としての人生を、一歩ずつ歩んでいきましょう。
【2月限定/先着10名のプレゼントを公開中】
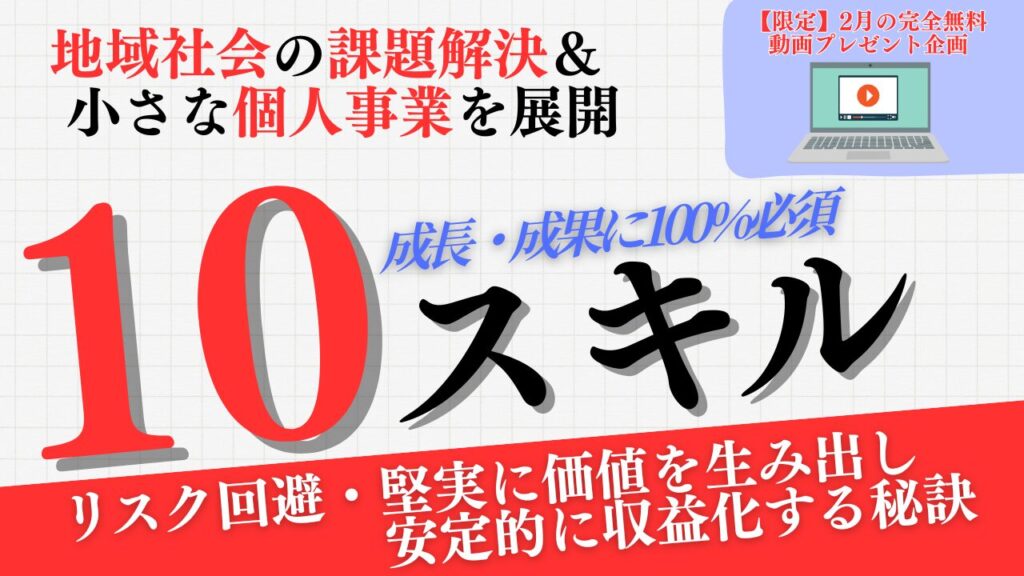
無料で基本から学べる動画を10本お届け!
1本あたり5分ほどでサクッと学ぶことができます。
いつでもどこでも学べる貢献型ひとり起業のノウハウ
自宅でもカフェでも通勤電車の車内でも、ネットがつながる環境ならしっかり学べます!
会員サイトには、その他「起業」「収益化」「価値創造」「貢献」「自己管理」「習慣改善」「学習効率化」など多数のコンテンツを公開しています。
一部ダウンロード可能なコンテンツもありますので、聞き流しながらマインドセットを固めスキルを高めることができます。
さらに!早期申込特典アリあとわずか!
期間・人数を限定してお届けしています。
(リンクが切れている場合は申込終了となっています。ご了承ください)
⚠️注意:こんな人はすぐに登録を解除します。
「誰かの役に立ちたい」「自分らしさを活かした仕事がしたい」「大切なものを守るために解決したい問題や課題がある」という方を対象とした学びの場ですので、「お金が儲かればなんでもいい」という方はお断りです。
「ノウハウだけが欲しい」
「学びや実践をする気はないけど、ちょっと内容が知りたい」
という方は、成長もしませんし、成果も出ません。
次のような方は今すぐご登録ください。
もし、
- 「目の前の人の役に立ち、社会で自分の役割を果たす」
- 「安定的な収益化と健全な資金繰りで事業を成長させたい」
- 「自分自身の健康や大切な人との時間を守りたい」
という想いをお持ちなら、「想いを言葉にする」「小さく実践をする」ということを繰り返しながら、「共感」をベースに事業を成長させていきましょう。
私も全力で、提供できる限りの情報をお届けしていきます。


