社会福祉士・起業家・コーチの『できない』リーダーシップとは?
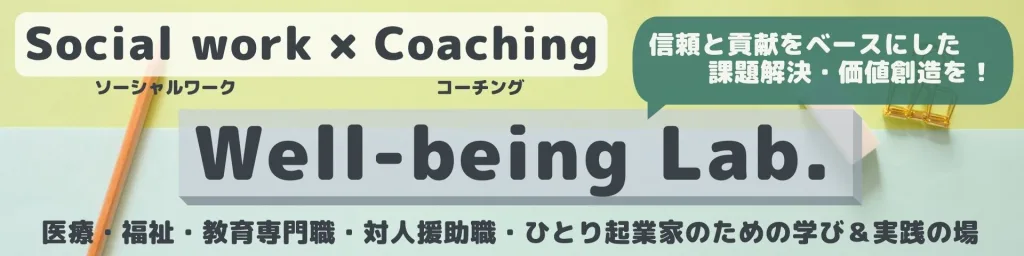

こんにちは!森山です。
今回は
挑戦し人を巻き込み成長しながら成果を残す「リーダーシップ」
についてお伝えしていきます。
今いる環境に不満があり、この状況を生み出しているのは組織の上層部にあることは明らかだけど、このまま何も変わりそうがない
私はこう感じることがたくさんありました。
とはいえ、

自分自身がリーダーシップを発揮するのは、なんだか怖い。
そう感じていました。
それから、自分一人でできることについてチャレンジを重ね、今では少しずつ共感を集めて活動範囲を広げることができています。
最近になって、

森山さんは組織の作り方やリーダーシップについてどんなふうに学んだんですか?
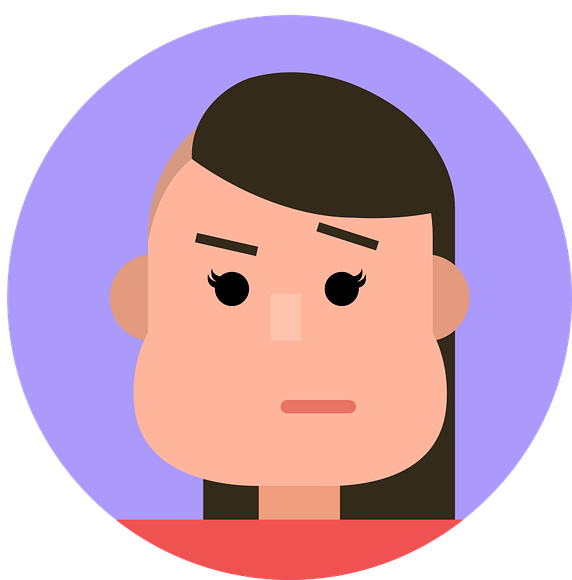
人を束ねたり、チーム全体で成長できる組織の作り方について教えてください。
そう尋ねられることも多くなってきました。
そこで、私自身の起業家、ソーシャルワーカー、コーチとしての経験から「共感をもとに仲間を集めチームを作ること」「未来を見据えて成長し成果を残すリーダーシップ」などについてお伝えできればと思います。
これは私が「複雑な状況下でチームで壁を乗り越える時、どうすればうまくいくのか」という問いに何度も向き合ってきた経験と学びの中からお伝えします。
理想と現実のギャップ、価値観の違う人との対話、なかなか進まないプロジェクト──。
そのたびに、スキルや知識の重要性を感じつつも、それだけでは突破できない「何か」があると気づかされます。
そんなとき、私の中に残り続けている、まちづくりに関する講座での講師の言葉を私なりに紐解きつつお伝えできればと思っていますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
Contents
まちづくり講義で教わる赤ちゃんリーダーシップ
10年くらい前に知り合った、尊敬するまちづくりの先生がいます。
「少し年上の兄貴」のような感覚と、「まちづくりに関する情熱と専門性」を併せ持つような方です。
話も文章も非常に面白く、芯にある考え方は鋭く、本質を突いている。
そんな先生です。
その方が講義の中で話してくれた印象的なエピソードがありました。
「まちづくりを進める上で、複雑な人間関係をまとめてリーダーシップを発揮できる人って、どんな人ですか?」
私がそう質問したとき、先生は次のように答えたんですね。
「赤ちゃんだよ」
一瞬、意味がわからず笑ってしまったけれど、話を聞いていくうちに、その答えが持つ深さに気づかされました。
一番何もできなくても人を動かす状況が生まれる
講義中に赤ちゃんが泣き出したら、親は「迷惑になる」と思って退室しようとするかもしれません。
でも、周りの人が「ここにいていいよ」と声をかけ、赤ちゃんを代わる代わるあやしながら、全員で講義を聞けるような雰囲気を作る。
こんな状況が生まれたらどうでしょう?
その場の空気が一体感を持ち、参加者が自主的に動き出す。
一人ひとりが自分の役割を見つけ始める。
このまとまりを生んだきっかけは、もしかすると赤ちゃんかもしれない。
つまり、“できない存在”が場をまとめたということです。
赤ちゃんには「自分でなんとかする力」がない。
だからこそ、人は自然と助け合い始める。
そして、その状況の中で、関係性の質が変わっていく。
起業家・ソーシャルワーカー・コーチという役割
私たちは、何かのゴールに向かって動いています。
起業家であれば、価値を生み、循環させること。
ソーシャルワーカーであれば、誰かの課題に寄り添い、社会との橋渡しをすること。
コーチであれば、相手の可能性を信じ、ゴール達成をサポートすること。
このようなことを考えた時に「自分が頑張らないと」「自分が周りを引っ張らないと」と力んでしまうことがあります。
それが空回りを産んだり、焦りからコミュニケーションエラーを生じさせてしまう。
関係性を悪化させ、共にゴールを見据えることができず、感情論でぶつかってしまうと最悪です。
ゴール設定→ゴールの共有→自分の役割を果たす
だからこそ「ゴールを設定し共有すること」ができたら、時にリーダーは「独断で行動する」のではなく「チームとして最大の成果を上げるような仕組みを作る」ということ。
これがリーダーの役割になるかもしれません。
リーダーシップやチーム・組織マネジメントについて考えたとき、私たちはつい、「自分がなんとかしなきゃ」「うまく導かなきゃ」と思い込んでしまいます。
でも実際には、「完璧であろうとする」ことよりも、「できないことを認められる」ことの方が、人を動かす原動力になることもあるということを、「赤ちゃんリーダーシップ」から学びました。
恐怖で支配するようなリーダーシップは古い
昔は、人を動かそうとする時に「利益をちらつかせる」とか「恐怖心を煽る」ということをしていた組織もあったかもしれません。
でも、「利益を感じなくなると裏切られる」ということは容易に想像できますうよね?
また、「恐怖を使った支配」は、その人が本来持つ能力を制限しますし、組織として負の影響をもたらすことが多いだけでなく、支配された人はたまったものではありません。
だからこそ、組織の構成員の意思の力で、チームとしての成果を最大化させる方法を考えること。
これがこれからの時代に求められるリーダーシップだと思っています。
リーダーが想いを語ること!助けを求めてもOK!
今お伝えしたように、人をまとめる力とは、決して「支配する力」ではありません。
リーダーとして大事なのは「想いを語る」「助けを求める」ということなのかもしれません。
「何でもこなせる」ことが条件でもありません。
むしろ、「私はここが弱い」「助けてほしい」と弱さを認め口に出すこと。
それを素直に言える人こそが、周囲の自主性を引き出し、関係性を豊かにしていきます。
これは、ビジネスでも、家庭でも、地域でも、同じことが言えると思います。
冒頭紹介したまちづくりの先生が、
夫婦や家族は、最小の「まち」とも考えられますね…
ということをおっしゃっていました
仕事やプライベートでの人間関係において起きることは、社会の縮図です。
誰か一人が全てを背負う必要なんてない。
できないことがあるからこそ、人はつながり、助け合うのだと私は考えています。
起業家リーダーシップ:関係性の中で生まれる循環
また、自分の事業が目指す未来や社会的な価値を考えたとき、「どう稼ぐか」「どう成果を出すか」以上に、「どう人と関係するか」「どう助けを受け取るか」が重要になる場面が出てきます。
強くて完璧な起業家ではなく、弱さを見せられる起業家。
何でも知っているコーチではなく、一緒に悩むコーチ。
与えるだけではなく、受け取れるソーシャルワーカー。
そんな存在こそが、信頼を生み、変化を起こす起点になるのではないかと思うのです。
あなたはどんな理想を描き共感を生み出しますか?
ここまで、リーダーシップは「できること」ではなく「できないこと」を通じて、関係性を育むこともできることを見てきました。
助け合い支え合い、高め合う中で、経済的な循環や社会的なインパクトが生まれてきます。
「何ができるか」よりも、「誰と、どんな関係を育てたいか」を起点にした事業のあり方を、私はこれからも模索していきたいと思っています。
あなたが今、目の前の人とどんな関係をつくろうとしているのか。
どんな“まち””コミュニティ”をつくろうとしているのか。
この記事が、そんな問い(ゴール設定)に向き合うきっかけになれば嬉しいです。
【2月限定/先着10名のプレゼントを公開中】
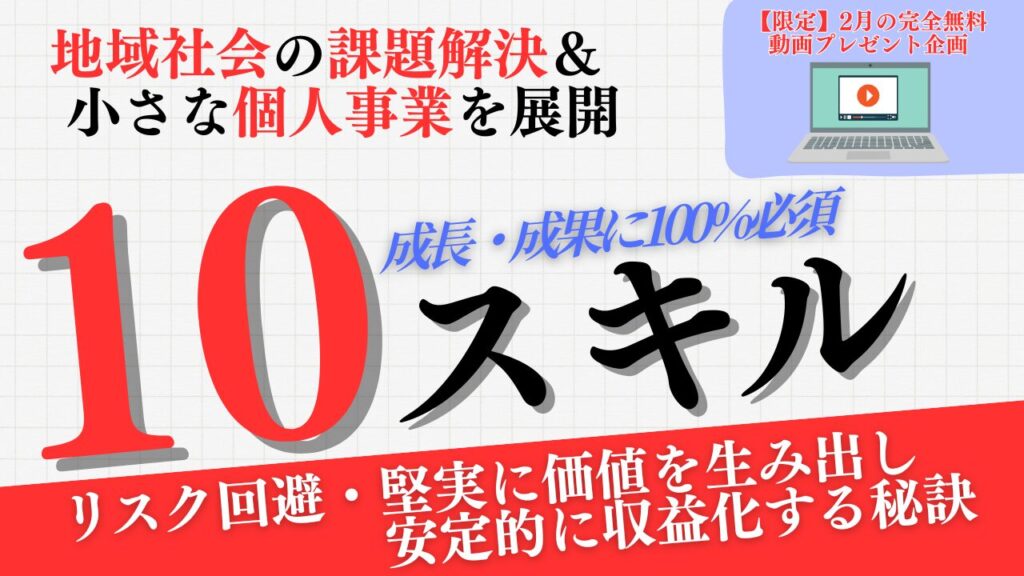
無料で基本から学べる動画を10本お届け!
1本あたり5分ほどでサクッと学ぶことができます。
いつでもどこでも学べる貢献型ひとり起業のノウハウ
自宅でもカフェでも通勤電車の車内でも、ネットがつながる環境ならしっかり学べます!
会員サイトには、その他「起業」「収益化」「価値創造」「貢献」「自己管理」「習慣改善」「学習効率化」など多数のコンテンツを公開しています。
一部ダウンロード可能なコンテンツもありますので、聞き流しながらマインドセットを固めスキルを高めることができます。
さらに!早期申込特典アリあとわずか!
期間・人数を限定してお届けしています。
(リンクが切れている場合は申込終了となっています。ご了承ください)
⚠️注意:こんな人はすぐに登録を解除します。
「誰かの役に立ちたい」「自分らしさを活かした仕事がしたい」「大切なものを守るために解決したい問題や課題がある」という方を対象とした学びの場ですので、「お金が儲かればなんでもいい」という方はお断りです。
「ノウハウだけが欲しい」
「学びや実践をする気はないけど、ちょっと内容が知りたい」
という方は、成長もしませんし、成果も出ません。
次のような方は今すぐご登録ください。
もし、
- 「目の前の人の役に立ち、社会で自分の役割を果たす」
- 「安定的な収益化と健全な資金繰りで事業を成長させたい」
- 「自分自身の健康や大切な人との時間を守りたい」
という想いをお持ちなら、「想いを言葉にする」「小さく実践をする」ということを繰り返しながら、「共感」をベースに事業を成長させていきましょう。
私も全力で、提供できる限りの情報をお届けしていきます。


