ひとり起業家・社会福祉士のための「超」実践的情報収集3つのポイント
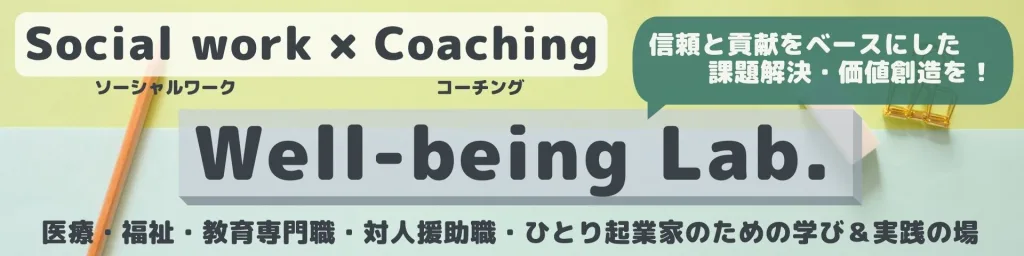

こんにちは!森山です。
今回は
効果的な情報収集3つのポイント
についてお伝えしていきます。

「頑張っているのに成果が出ない…」
「その原因がなんだかわからない。どうしたらいい?」
ひとり起業家や地域活動に取り組む方の相談に乗っていると、「問題ははっきりしないけど成長もなく成果も上がらない」という悩みを抱えることがよくあるそうです。
その原因のひとつが、
「情報収集の甘さ」
にあるかもしれないということを、私自身の経験からは思うんですね…。
社会福祉士としての支援活動でも、起業家としての事業運営でも、成果を出すためには 適切な情報を集め、分析し、活用する力 はめっっっちゃ大切!
しかし、情報収集の方法を誤ると、どれだけ努力しても見当違いのアクションになり、時間も労力も水の泡になって全てパァです。
そこで今回は、 「本当に役立つ情報」を集めるための3つのポイント を、私自身の経験も交えながら解説します!
この記事を読めば、 社会貢献や起業において成果を出すための情報収集のコツ がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
質の高い情報ソース&一次情報を重視
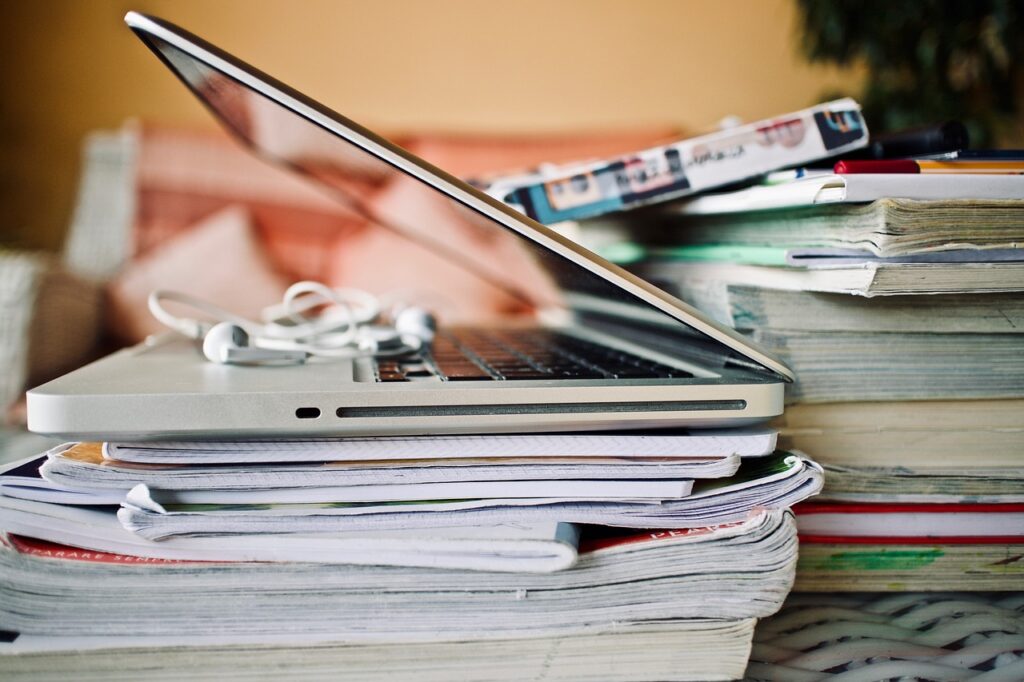
情報収集の第一歩は、「どこから情報を得るか」です。
ここを間違えると、誤った判断をしてしまう危険があります。
こんな情報収集はNG!
実際に情報収集する上で、「薄っぺらく信用に足らない情報を鵜呑みにするのは危険です。
なぜか?
それらを鵜呑みにすることで「判断を誤る」「無駄な仕事が増える」「迷いが深まる」という状態が起こるからです。
例えば、
- ネット検索だけで済ませる(情報が古かったり偏っていたりする)
- 出どころ不明のSNS情報を鵜呑みにする
- 机上のリサーチだけで、生の声に触れたり現場に行ったりしない
このようなことは超危険だということについては、最低限意識を持っておくようにしてください。
こんな情報収集が大事!
実際に情報収集をする上では、
- 専門家や信頼できる機関のデータを活用する
- 現場に足を運び、一次情報を集める
- 実際に話を聞く(クライエント・地域住民・現場の職員・顧客)
このような実践が大事です。
社会福祉士の実践で学んだ情報収集の実際
例えば社会福祉士としての支援であれば、クライエントの話を直接聞くことはもちろん大事です。
さらに、その人を取り巻く 「環境」 に目を向けることも重要です。
- 家庭の状況は?
- 職場でのサポート体制は?
- 退院後や就職後の生活はどうなる?
このような「パッとみるだけでは気づきにくいこと」に対してもアンテナを貼って、見つめ直していくことが大事です。
起業家としての実践で超速で成果が上がった情報収集法
また、起業家であれば、市場リサーチ で机上のデータだけを見るだけではダメです。
私が実際に起業家として成果が上がるようになったのは「顧客」「見込み客」とコミュニケーションをとるようになってからです。
つまり、実際に悩みを抱えた人が考えていることや生の声を聞くこと が重要です。
- 販売現場に行ってみる
- 競合の商品を試してみる
- 顧客インタビューを行う
こうした 「意味ある情報」 を得ることで、価値あるアクションにつながります。
多角的な視点で分析する:偏った判断を防ぐ

情報収集の次に大事なのが 「分析方法」 です。
「情報を集めたのに、判断を誤る…」というのは、 視点が偏っている ことが原因かもしれません。
こんな分析の仕方はNG!
もしかすると、
- 自分の専門知識だけで判断する
- 目の前の課題に囚われ、将来の影響を考えない
- 自分の仮説を確かめるための情報だけを探す(確証バイアス)
このようなことをしていませんか?
分析に偏りがあると、実践で結果を出せなくなってしまう可能性があります。
こんな分析が大事!
そこで、
- 異なる分野の専門家の意見を聞く
- 「未来の視点」も考える
- 壁打ち(フィードバック)を受ける
このようなことができる環境・習慣を当たり前にしておくこと。
これがものすごく大事です。
福祉の視点と医療の視点|起業家の視点と顧客の視点
例えば、福祉の視点で見れば「この人は退院できる」と判断しても、医療やリハビリの視点では「退院後の生活が難しい」という見立てになることもあります。
また、ひとり起業家の場合、「これは売れる!」と自分で思っていても、マーケットの専門家や顧客の意見を聞くと 「求められていない」 ということもあるでしょう。
自分だけで考えると心理的盲点や偏りが生じる
このように、「自分だけで考えようとする」と心理的盲点が生まれ、認識から漏れ落ちてしまう情報があるということ。
そして、「自分だけで考える」ということをしたら「偏った見方になってしまう可能性がある」ということ。
これらを知っておきつつ、「情報収集」「分析」を継続していくことが求められるんですね。
相談や壁打ちの重要性
このような「心理的盲点」「バイアス(偏り)」がありながらも、上手に「情報収集」「分析」をするためにはどうしたらいいでしょうか?
私の経験では「相談」「壁打ち」などがシンプルでありながらめっちゃ有効だと考えています。
具体例:壁打ちを実践してみる
例えば「壁打ち」についてですが、「この事業アイデアはどう思いますか?」 と話してみると、自分では気づかなかった盲点をいくつも指摘してもらえるかもしれません。
そこで「事業の方向性見直す」ということでもいいですし、修正を重ねてトライしてみるのもいいかもしれません。
具体例:他者の目線から自分の強みを見出す
また、「自分の強みや課題を、他者の視点で見てもらう」という意味でも、他者の意見を聞くことは大事です。
というのも、自分の強みや課題って、自分では意外と気づきにくいからです。
そして、ビジネスを展開するという意味では、プロの目線から「競合と比較して分析すること」「自分の立ち位置を客観的に把握すること」も大事です。
このように、 「第三者の視点」 を取り入れることで、より正確な判断ができるようになります。
情報の検証と実践:小さなアクションで確かめる

最後に、情報収集の最大のポイントは 「実際に確かめること」 です。
どれだけリサーチしても、行動しなければ 「机上の空論」 になってしまいます。
こんな失敗をしがち!
実際にお話を伺っていて、
- 情報を集めるだけで満足する
- すべての情報を揃えてから動こうとする(完璧主義)
- 「やってみないと分からない」ことを考えすぎて動けない
という状態に陥ってしまう方は非常に多いです。
実践的な検証方法!
実践的な検証としては、
- 小さなテストを繰り返す(リーンスタートアップ)
- 仮説を立てて実験し、データを集める
- 情報収集の結果をすぐに活用する
このような意識で行動することで、実践の精度を上げながら、成長しつつ成果を掴み取ることができるんです。
起業家の「テスト」戦略
例えば、起業家であれば 「売れるか分からない商品を、まずは試験的に販売してみる」 という戦略を取ります。
- SNSでテスト販売してみる
- 小規模なイベントを開いて、お客さんの反応を見る
- 簡単なLP(ランディングページ)を作って、どれだけ反応があるかを測る
このようなことを小さく実践しながら、振り返りと改善を続けていくんですね。
ソーシャルワーカーの継続的なアセスメント
社会福祉士・ソーシャルワーカーの場合、インテーク・アセスメント・プランニングという流れをじっくり取るのが基本です。
ただ、いつもそれができる余裕があればいいですが、緊急の介入が必要な場合もあります。
緊急時などは即介入が必要ですし、十分な情報が収集できない状態でも、介入をしながら必要な情報を継続的に収集していくことが求められます。
ご本人の反応や環境の変化を「実践」「介入」をしながら観察するわけですね!
そして継続的なアセスメント(情報収集と分析)を重ねつつ次なる支援の方向性を模索していくんです。
まとめ:情報収集は「活用」してこそ意味がある

情報収集の目的は、「正しい判断をし、成果を出すこと」です。
そのためには、次の3つのポイントを意識しましょう。
- 質の高い情報ソースを選ぶ(一次情報を重視)
- 多角的な視点で分析する(偏った判断を防ぐ)
- 情報を検証し、実践する(小さなアクションを繰り返す)
情報収集は「集めて終わり」ではなく、「行動につなげる」ことが最も大切です。
今日からできる実践ポイント
では、今回の内容を踏まえて「今日からできる実践ポイント」についてお伝えします。
- 信頼できる情報源を探す
- 壁打ち相手を見つけ、フィードバックをもらう
- 小さなアクションを起こし、情報を検証する
この習慣を身につけることで、ひとり起業家としても、社会福祉士としても、より確かな成果を出せるようになります。
ぜひ、実践してみてください!
【2月限定/先着10名のプレゼントを公開中】
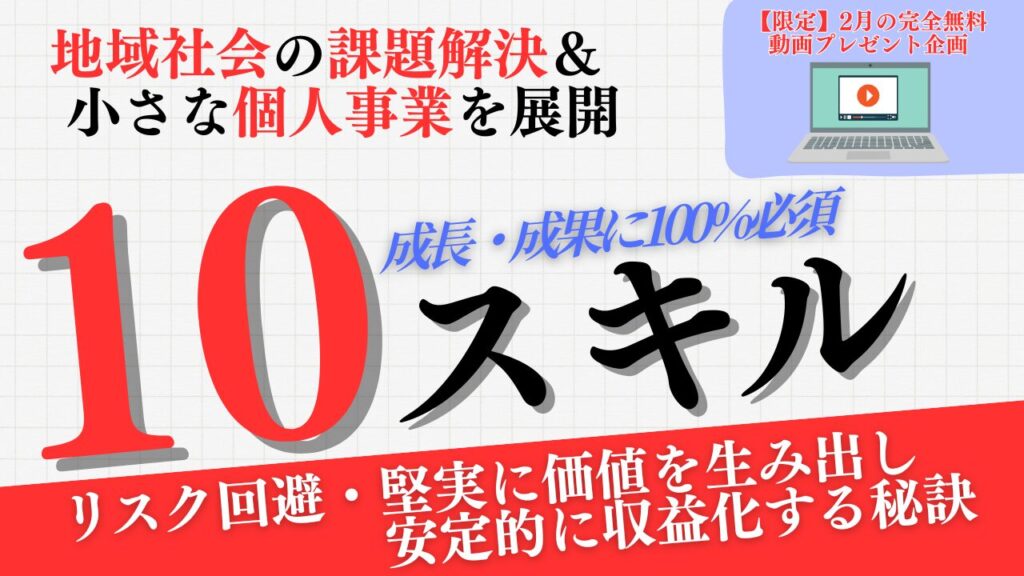
無料で基本から学べる動画を10本お届け!
1本あたり5分ほどでサクッと学ぶことができます。
いつでもどこでも学べる貢献型ひとり起業のノウハウ
自宅でもカフェでも通勤電車の車内でも、ネットがつながる環境ならしっかり学べます!
会員サイトには、その他「起業」「収益化」「価値創造」「貢献」「自己管理」「習慣改善」「学習効率化」など多数のコンテンツを公開しています。
一部ダウンロード可能なコンテンツもありますので、聞き流しながらマインドセットを固めスキルを高めることができます。
さらに!早期申込特典アリあとわずか!
期間・人数を限定してお届けしています。
(リンクが切れている場合は申込終了となっています。ご了承ください)
⚠️注意:こんな人はすぐに登録を解除します。
「誰かの役に立ちたい」「自分らしさを活かした仕事がしたい」「大切なものを守るために解決したい問題や課題がある」という方を対象とした学びの場ですので、「お金が儲かればなんでもいい」という方はお断りです。
「ノウハウだけが欲しい」
「学びや実践をする気はないけど、ちょっと内容が知りたい」
という方は、成長もしませんし、成果も出ません。
次のような方は今すぐご登録ください。
もし、
- 「目の前の人の役に立ち、社会で自分の役割を果たす」
- 「安定的な収益化と健全な資金繰りで事業を成長させたい」
- 「自分自身の健康や大切な人との時間を守りたい」
という想いをお持ちなら、「想いを言葉にする」「小さく実践をする」ということを繰り返しながら、「共感」をベースに事業を成長させていきましょう。
私も全力で、提供できる限りの情報をお届けしていきます。


