社会福祉士・ひとり起業家|相談業務や対人援助で信頼を損なう人の落とし穴
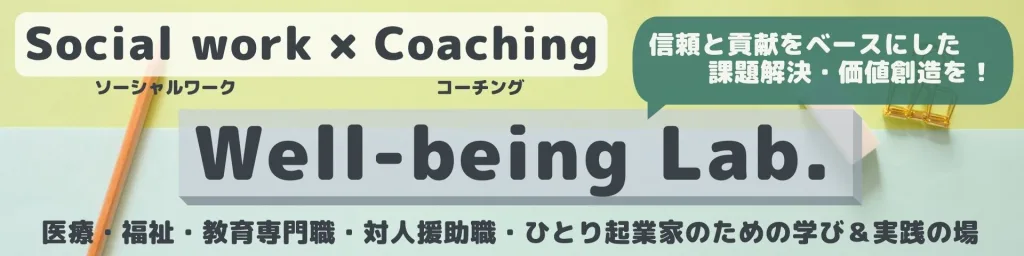

こんにちは!森山です。
今回は
相談業務や対人援助で信頼を損なう人の落とし穴
についてお伝えしていきます。
相談業務や対人援助で最も大切なこととは何ですか?
もし、このように聞かれたら、何と答えますか?

そりゃ、クライエントさんに寄り添って支援することでしょう…
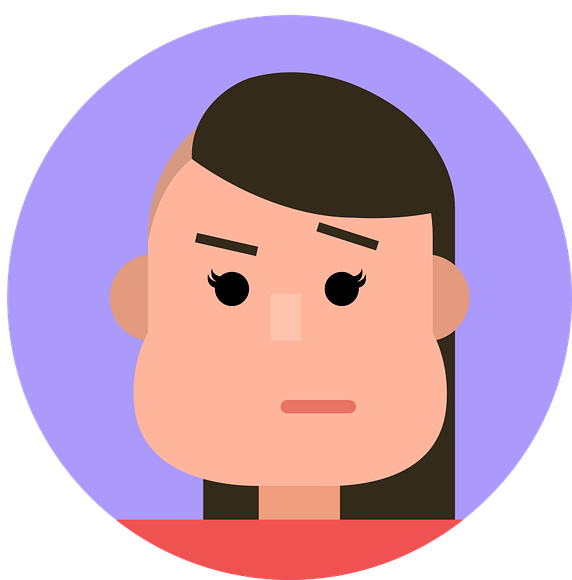
傾聴して信頼を育むことだと考えています。
そう、いろんなアンサーが考えられそうですよね…。
私も社会福祉士・コーチ・講師・起業家などといろんな役割をこなす中で、
- 信頼を損なってしまった
- 自分の役割を見失った
というような苦い経験がたくさんあります。
そこでこの記事では、そんな私の失敗を思い出しつつ、田中さん(仮名)からのご相談内容からの改めて気づきをシェアし、相談支援や対人援助で大切なポイントを一緒に確認していきたいと思います。
興味がある方はぜひ最後までチェックしてみてください!
Contents
田中さんのご相談:「話が合わない」と感じて辛いです

今回ご相談をくださったのは、オンラインを通じてつながった田中さん(仮名)という方です。
(今回はご本人の承諾を得たうえで、相談内容を一部伏せつつ共有させていただきます。)
誰とも話が合わないのは誰が悪い?
田中さんのお悩みは、「どのコミュニティにいても、誰とも話が合わないと感じてしまう」というものでした。
職場、地域、学生時代の仲間、趣味の集まり、家族関係、パートナーとの間でも、「価値観が違いすぎてしんどい」と感じる場面が多いとのこと。
そこで、「相手を我慢させる」のは嫌だし「自分が我慢する」ということをしようとして疲弊してしまうというのです。
「自分は人と分かり合えないんだ」と思い込んでしまう
話を丁寧に聞いていくと、過去に何度も人間関係でのトラブルやすれ違いがあったそうです。
それが積み重なって「自分は人とわかり合えない」と思い込んでしまっている。
そんなことが彼女の話から見えてきました。
相談員・対人援助職に「指摘されること」で深まる自己否定

実は田中さんは私のもとに来る前に、別の方に相談をされたとのことでした。
オンラインで見つけた「ライフコーチ」「コミュニケーション講師」という肩書きの方のお話を聞いたそうです。
田中さんの話を受け止めず「問題解決のための指導」が…
田中さんはこの時、話を聞いてもらったという実感を得られなかったとのことです。
そして、限られた時間のセッションの中で「まずあなたのこの考え方がズレていますね…」「こういうところを直さないとダメですよ!」と、問題点を指摘されたといいます。
「自分が悪い」「自己嫌悪」「追い詰められる」
その結果、「やっぱり自分が悪いんだ」と感じてしまい、自分を否定し、どんどん追い詰められていったそうです。
「どうすれば直せるか」ばかりに意識が向いてしまい、そもそも何がつらいのか、どんな背景があるのかを見てもらえないまま、苦しさが残ってしまった。
私はもはやどこにも馴染めないの?
その後、「私はもう、どこにも馴染めない人間なのかもしれない」と深く思い込むようになってしまったとのことです。
そして、「社会福祉士」「コーチング」などの検索ワードをもとに、私の情報へ辿り着き、相談に来られました。
相談員・対人援助職として忘れてはいけないこと
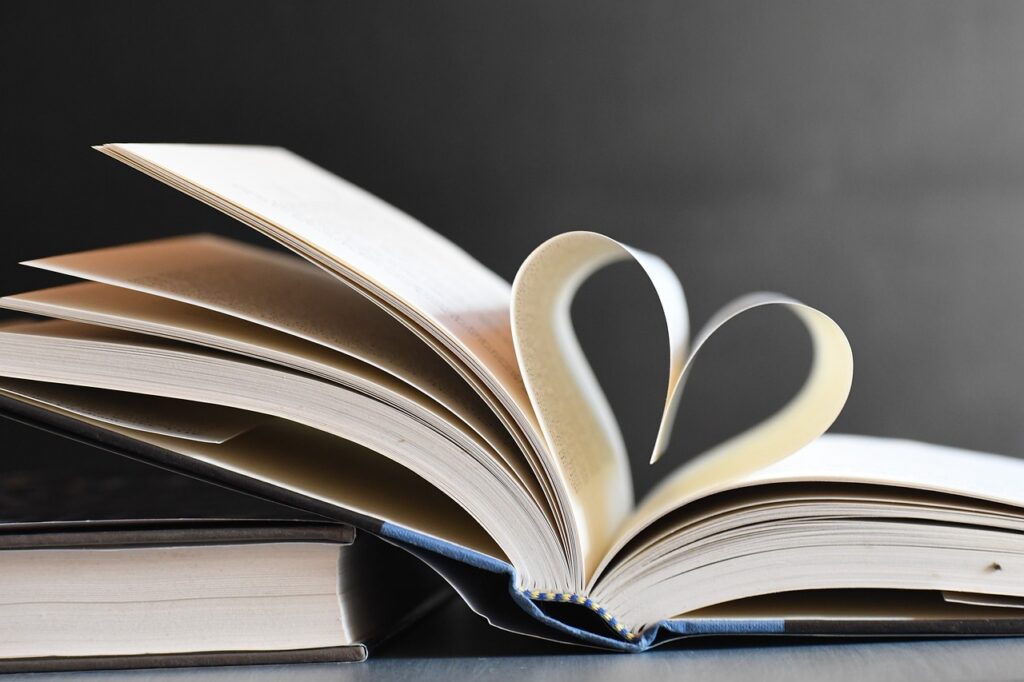
このエピソードを通して私が改めて感じたのは、
「相談に乗る側のあり方」が、相談者の自己理解や回復に大きく影響する
ということです。
自分の在り方を理解し受け止めよう
人は誰しも、悩みを抱えているとき、自分自身のことを否定的に捉えやすくなっています。
そんなときに、いきなり「それは間違っています」「あなたのここが問題です」と言われると、どうでしょうか?
どうしても心は閉じてしまいませんか?
アドバイスや問題解決に舵を切る→信頼構築&アセスメントの後
基本として大切なのは、すぐにアドバイスをすることではありません。
まずその人の経験や感じていることに丁寧に寄り添い、「今、どんな背景があるのか」をアセスメントすること。
そして、相談に来てくれた相手との間に「信頼関係」を築くこと。
それこそが、相談者の力を引き出すための第一歩だと私は考えています。
「わかる」を「できる」に!「できる」を「当たり前」に!

今お伝えしたことって「頭では理解できる」はずです。
さらには、対人援助職としての体系的な学びを経た方なのであれば、「すでに教科書で習って知っている」ことでもあるはず。
プロのコミュニティでもわかっていないしできていない?
でも、私も社会福祉士の集まりや、コーチのコミュニティ、教育系起業家との話の中で、「信頼関係の構築を蔑ろにしている人」「アセスメントの重要性を理解していない人」がたくさんおられることに驚いてきました。
もちろん、そのような状態では実戦において結果は出ていないようです。
その原因を、あたかもクライエントの努力不足とか、自分の指導者や所属する組織の責任にしている方もおられて、もはや呆れ果てて何もいうことがありませんでした。
「できるかどうか」より「やりたいかどうか」→学ぶ姿勢
私も含めて、対人援助職として大事なのは「学ぶ姿勢」ではないでしょうか?
わからないから学ぶし、学んで理解したとしてすぐにはできるようにならないから繰り返す。
このように、学びと実践を継続してこそ、一つ一つの学びが自分自身の成長につながり、成果となっていくのではないでしょうか?
まとめ:支援は「評価」ではなく「関係」から始まる

私は今回の田中さんからのご相談を受けていて、
- プロとして自覚を持ち、自分の役割や在り方を考えること
- 相手の話をしっかりと受け止め信頼構築や情報収集を徹底すること
- その上で、必要に応じて助言をするなど、クライエントの力を信じて支援にあたること
このような基本でありながら重要なポイントを改めて振り返ろうと思い記事にしました。
何も考えず相手の問題を指摘してどうする?
相談を受けるというのは、決して「相手の問題を指摘すること」ではありません。
むしろ、「この人なら話せる」「ここなら自分を出しても大丈夫」と感じてもらえる場をつくることの方がずっと重要です。
クライエントに対して自分はどう在るのか?
特に、支援職やコーチとして人に関わる立場の方には、「問題解決」よりも前に、
「その人の味方である姿勢」「相手を尊重するまなざし」
を持ち続けてほしいなと、心から思います。
田中さんのように、誰かがつらさを抱えて相談してきてくれたとき、
その人が「否定されることなく、ちゃんと理解してもらえた」と感じられるような関わりを、これからも大事にしていきたいですね。
【2月限定/先着10名のプレゼントを公開中】
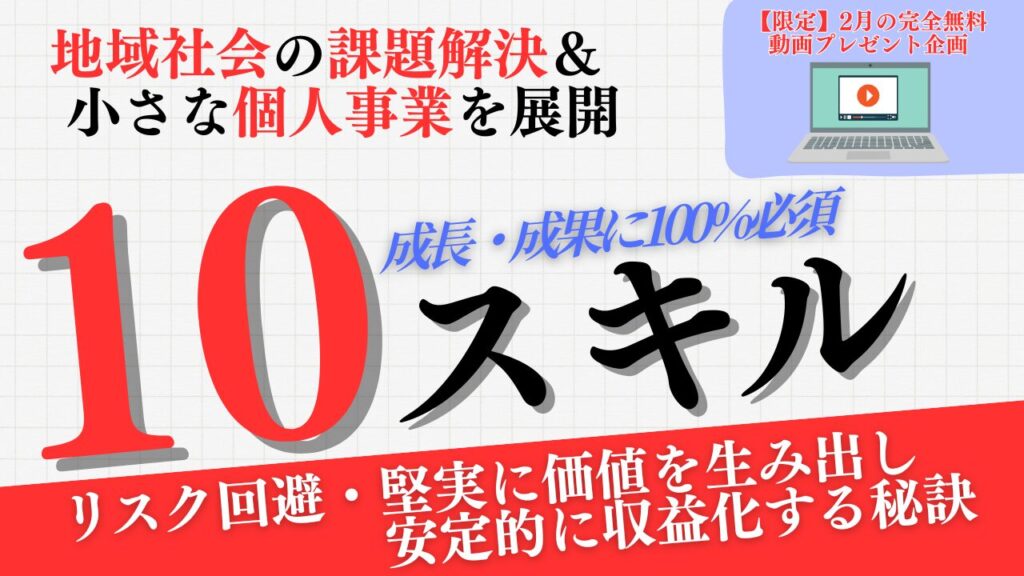
無料で基本から学べる動画を10本お届け!
1本あたり5分ほどでサクッと学ぶことができます。
いつでもどこでも学べる貢献型ひとり起業のノウハウ
自宅でもカフェでも通勤電車の車内でも、ネットがつながる環境ならしっかり学べます!
会員サイトには、その他「起業」「収益化」「価値創造」「貢献」「自己管理」「習慣改善」「学習効率化」など多数のコンテンツを公開しています。
一部ダウンロード可能なコンテンツもありますので、聞き流しながらマインドセットを固めスキルを高めることができます。
さらに!早期申込特典アリあとわずか!
期間・人数を限定してお届けしています。
(リンクが切れている場合は申込終了となっています。ご了承ください)
⚠️注意:こんな人はすぐに登録を解除します。
「誰かの役に立ちたい」「自分らしさを活かした仕事がしたい」「大切なものを守るために解決したい問題や課題がある」という方を対象とした学びの場ですので、「お金が儲かればなんでもいい」という方はお断りです。
「ノウハウだけが欲しい」
「学びや実践をする気はないけど、ちょっと内容が知りたい」
という方は、成長もしませんし、成果も出ません。
次のような方は今すぐご登録ください。
もし、
- 「目の前の人の役に立ち、社会で自分の役割を果たす」
- 「安定的な収益化と健全な資金繰りで事業を成長させたい」
- 「自分自身の健康や大切な人との時間を守りたい」
という想いをお持ちなら、「想いを言葉にする」「小さく実践をする」ということを繰り返しながら、「共感」をベースに事業を成長させていきましょう。
私も全力で、提供できる限りの情報をお届けしていきます。


