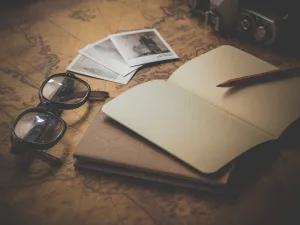社会福祉士・コーチが仕事や貢献活動でピンチの芽を摘むボランチ力
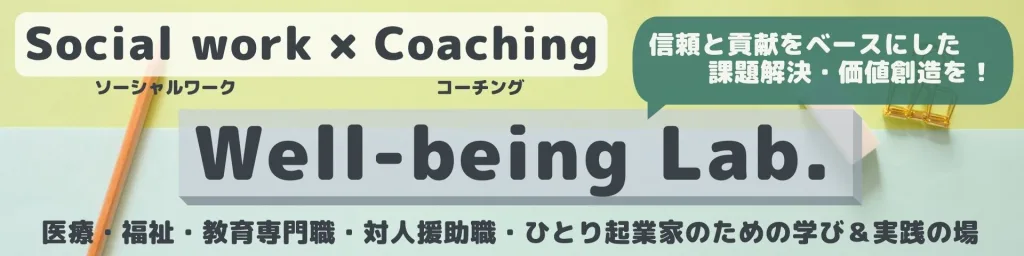

こんにちは!森山です。
今回は
サッカーのボランチに学ぶ「冷静さ」「判断力」の重要性
についてお伝えしていきます。
地域課題の解決に取り組んでいて、「冷静さ」と「高い判断力」は求められるなぁと感じさせられることが多いです。
感情的になりすぎたり、判断が遅れたり、誤った判断を続けると、思うような成果を出すことができません。
私が地域活動を通じて感じるのは、サッカーの「ボランチ(守備的ミッドフィルダー)」の役割に似た感覚が重要だということ…。
サッカーに詳しい方ならご存知だとは思いますが、ボランチは攻守の要となるポジションです。
ゲーム全体を見渡しながらチームのバランスを取る役割を担います。
この辺りを深掘りしてみていきますね!
Contents
ボランチの役割と地域活動の共通点〜社会福祉士の視点から〜

では、私がサッカーのボランチと地域活動に取り組む上で共通すると感じる点について整理してみていきますね!
全体を見てバランスを取る
地域活動において、目の前の問題だけにとらわれず、幅広い視野で全体の状況を把握しながら行動することはめっちゃ大事!
短期的な対応だけでなく、持続可能な解決策を考えるための広い視野がなければ、最初から結果が出ないと分かりきった取り組みに、時間や労力を奪われてしまうことがあります。
ピンチを察知し早めに芽を摘む
地域の課題は、放置するとより大きな問題に発展することがあります。
ボランチが相手の攻めを早めに察知し対応するように、地域課題も複雑化しないうちに手を打つことで、深刻な事態を防ぐことができます。
例えば、「組織の風通しが悪く、発言力が偏り、新たな人が参画できない状況」があるとします。
この課題をひどい時には5年・10年、ずっと抱え続けて何もできていないとしたら、今すぐ具体的なアクションをしてみた方がいいですね!
タイミングを見極め、積極的に挑戦する
地域での活動って、(もちろん組織の目指す内容によりますが)基本的には「守り」を意識し、「話し合いを重ねる」「関係性を大切にする」ということが大事だと思っています。
とはいえ、守り一辺倒ではなく、攻めるべき時には果敢に行動することも必要です。
ボランチが「ここぞ」という場面で決定的なパスやシュートを狙うように、地域活動においても、最適なタイミングで新しい取り組みを打ち出すこと。
このように、状況を見て「積極的な挑戦をしつつ」「リスクは常に管理する」ということが成功のカギとなると私は考えています。
まちづくりで「ボランチの感覚」を養うために

地域活動において、この「ボランチの感覚」を身につけるにはどうすればよいのでしょうか?
私自身も試行錯誤を続ける中で、3つのポイントが重要だと感じています。
1. 一喜一憂しすぎない
成功しても過度に喜びすぎず、失敗しても必要以上に落ち込まないこと。
これ、めっちゃ大事です!
感情に流されすぎず、冷静に状況を分析し、次の一手を考えることですね!
ただ私も油断するとすぐに感情に囚われてしまうので、日頃の生活習慣の中に「意識的に感情を整えるような工夫」を取り入れるようにしています。
2. 未来を見据えた挑戦を「楽しむ」
また、地域活動について「変わりゆく時代の中で今目の前のことに集中し、変化を楽しむ」という前向きな気持ちを持つことも大事だと考えています。
場合によっては地域活動・まちづくり活動や「10年単位」など短すぎるようなこともあり得ます。
一つの物事が動くのに「30年」かかったり、目の前の変化が50年〜80年影響を与えるようなものもあるわけです。
私がまちづくりについて学んでいたときに、講師をしてくださった方がイロコイ族と言うネイティブアメリカンの言葉を紹介してくださいました。
“In our every deliberation, we must consider the impact of our decisions on the next seven generations.”
「どんなことでも7世代先(セブンス・ジェネレーション)のことを考えて決めなくてはならない」
講師の先生にいよると、イロコイ族は1本の木を伐る時も、魚1匹捕るときも、常に「7世代先の子孫のためになるか、困らないか」という価値観を基準にして、その答えがNOであればその行為を止めるそうです。
まちづくりは、このように100年先の未来や200年・300年先の世代を見据えて行うことなのかもしれません。
このような思いを抱きつつ、目の前の状況に対して、自分の役割を考えながら、行動を続けることを私は大事にしています。
とはいえ、感情に囚われたり、困難な状況に直面することがあります。
そこは適度に力を抜きながら、壁を乗り越えるプロセス自体を楽しめるようになればいいですね!
3. 「幸せだから成功する」というマインドセット
また、私が尊敬する科学者が
「成功したら幸せになるのではない。幸せだから成功するんだ」
と言っています。
これはまさにその通りだと思うんですね。
仕事も、地域活動も、「幸せ」だから取り組むことそのものに喜びを感じ、成長しながら成果を上げられる。
結果が出たから「幸せ」で「充実する」のではなく、むしろその逆なんです。
活動そのものを楽しみ、前向きな気持ちを持つことで、行動力も発想力も最大化し、良い成果を生み出すことができる。
このことが実は「バランスを取る」「守りを固める」「挑戦をして成果を上げる」という意味で重要な気がします。
まとめ|果敢に挑戦しバランスをとる役割を!
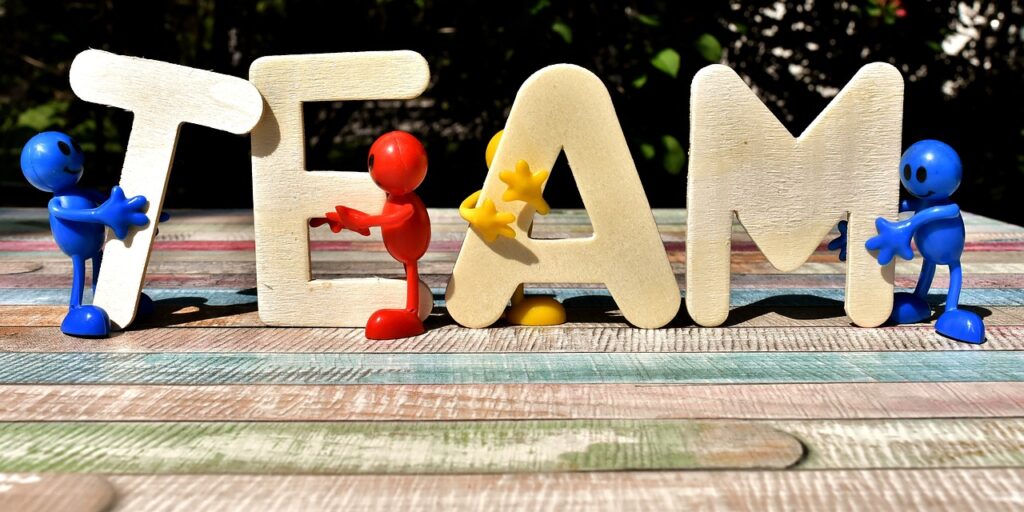
今回はサッカーのポジションである「ボランチ」を一つの切り口として情報提供してきました。
地域課題の解決には、感情に流されることなく、全体を見渡しながらバランスを取る「ボランチの役割」「ボランチの感覚」が不可欠ではないか?
そんな話をしてきました。
ピンチを察知し早めに芽を摘む&果敢に挑戦する
ピンチを察知し早めに対応しつつ、攻めるべき時には果敢に挑戦する。
この感覚を養うために、一喜一憂せず、挑戦を楽しみ、前向きなマインドを持ち続けること!
ぜひ、このことを頭に入れていただいて、できることから一つずつチャレンジしてみてください。
リーダーシップを育みバランス感覚を養う→小さく行動
実はボランチを務める人は「キャプテン」を任されることも多く、サッカー日本代表でも「遠藤航」や「長谷部誠」などはボランチです。
地域活動に携わる皆さんが、より効果的なアクションを取れるよう、この「ボランチの感覚」を意識して、小さなところからリーダーシップを発揮してみたり、果敢に挑戦したりバランスをとる役割を担ってみてはいかがでしょうか?
実践者としてソーシャルワーク・コーチングを学び直す
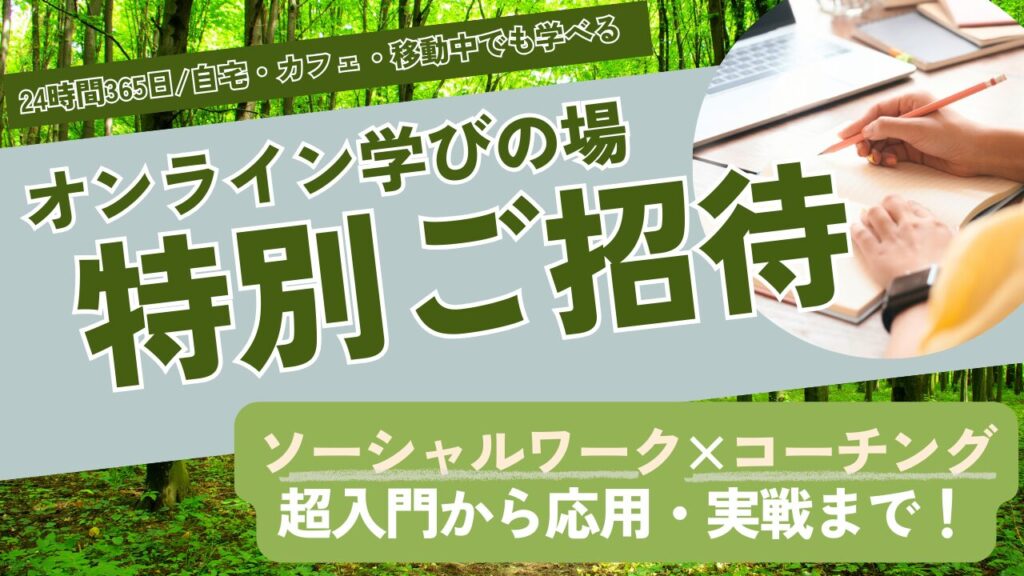
頑張っても疲れてしまう。優しさが奪われていく。そんなのは嫌だ!
ソーシャルワークやコーチングを学び、実践し、成果を出す。
- 目の前の人の人生を幸せなものに
- 優しいつながりを育み
- 豊かな・地域社会をつくる
このような「想い」を「形」にするために、私たちの役割や専門性について、もう一度考え直し、社会やこれからの時代を見据えて「私たちに何ができるか」を一緒に考えませんか?
早期申込特典アリあとわずか!
期間・人数を限定してお届けしています。
(リンクが切れている場合は申込終了となっています。ご了承ください)