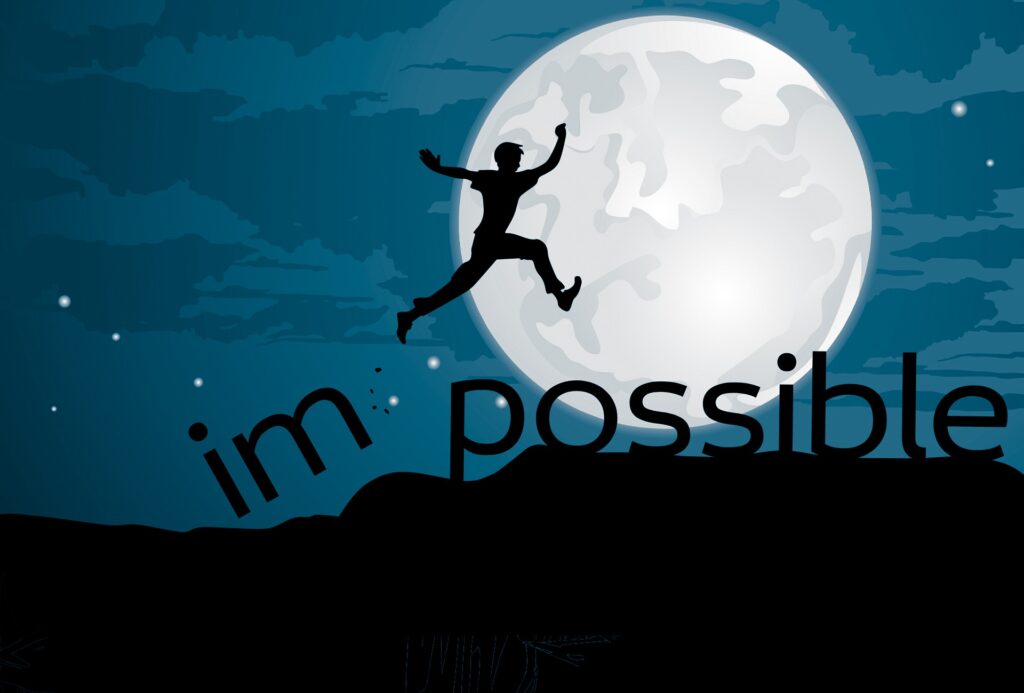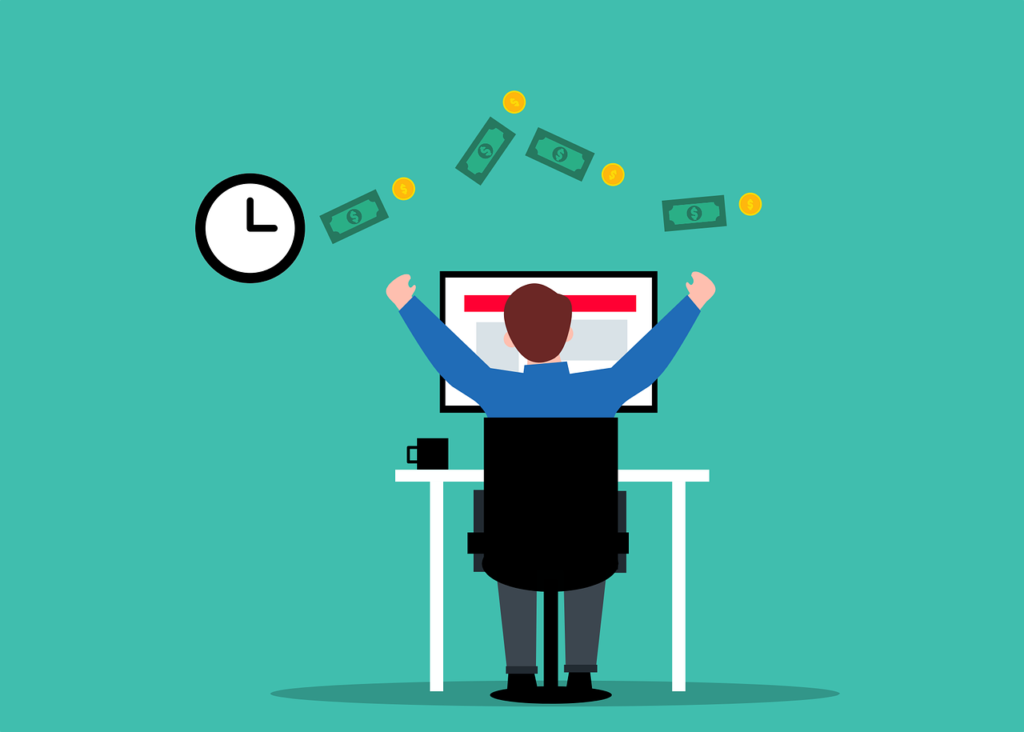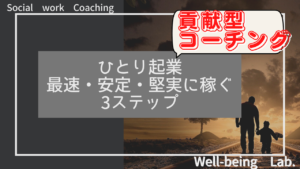社会福祉士がひとり起業!独立する3つのメリットと注意点&稼ぎ方
今回は
社会福祉士としてひとり起業・独立するメリットと注意点
についてお伝えします。

社会福祉士として起業したいと考えている方への動画での情報提供も行っていますので、ぜひ下記リンクも参考にしてみてください!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
社会福祉士が独立・起業する前に考えるべき3つのこと【貢献&収益化】
Contents
社会福祉士として起業したいなら必見の内容!
今回の記事では、安定的に収入を得る方法と、私が社会福祉士としてひとり起業する上で絶対に欠かせないと考えている思考法についてもお伝えします。
「社会福祉士の資格を取得して、いずれ起業したい」
このような強い想いをお持ちの方も、時代の流れや社会の変化を見据えて今のうちに何をすべきかが理解できます。
これから資格を取得されるという方も、知識習得やスキルアップと同時に事業立ち上げ準備にも着手し、実際の行動をスタートさせると事業の安定的な展開が流れるようにスムーズに行えるはずです。
また、現在社会福祉士として活躍していて
「私でも独立開業できるの?」
という疑問を持っている方は、起業することの可能性について知り、社会福祉士としての役割を最大限に果たしながら堅実な収益基盤を構築する方法をご理解いただけるはずです!
また、起業する際に知っておかなければいけない注意点についても一緒に確認していきましょう!
ぜひ最後までチェックしてみてください。
社会福祉士の専門性と情熱がある→起業はオススメ!
社会福祉士・ソーシャルワーカーとしてこれからも本気で実践を行いたいと考えるのであれば、
「起業」「個人での活動」「自分で事業を経営」などは個人的には超オススメの選択肢
だと考えています。
その理由はいくつもありますが、組織でのしがらみや業界独特の考え方によって、ソーシャルワーカーとしての活動を制限されることがないことも、ソーシャルワーカーとしてひとり起業・独立するメリットですね。
社会福祉士・ソーシャルワーカーがひとり起業!
私は障害福祉サービス、介護保険サービスの事業所で雇われて働いていた経験があります。
就労継続支援B型の事業所ではさまざまな障害を抱えながら働きたいという想いをお持ちの方に指導員として接する日々でした。
軽作業をこなしながらクライエントさんの思いに沿って生活上の悩みや不安に耳を傾け、将来を見据えてスキルを身につけるためのサポートをする仕事だったんですね…。
また介護保険サービスではデイサービスの相談員として認知症の方のQOLを高めるためのサポートと、家族の方との生活をより良いものにするための調整をしてきました。
仕事そのものにはやりがいを感じていました。
ただ、その一方で
- 慢性的な人手不足による多忙な業務と責任
- 組織の雰囲気や人間関係のストレス
- 低い給料などの待遇面
など、雇われて働く中での「不安」「不満」などが蓄積してきました。
そこで、
「ソーシャルワーカーとしてやりたいことをやり抜く!」「未来に向けて挑戦する」「家族との時間を大事にする」「経済的な基盤を固める」…
これらの想いから起業しました。
ひとり起業→不安や不満が解消!
今となっては心の底から「起業してよかった」と思っています。
なぜかというと、
起業を検討したときの「不安」「不満」は解消され、やりたいと思っていたことのいくつかは既に実現しているから
なんですね。
また、今後もやりたいことを追求していきますし、挑戦も続けたいと思っています。
将来を見据えて現状を変える→ひとり起業
ひとり起業をスタートした当時、
「家族との時間も十分にとりつつ経済的な基盤をより強固にしたい…。」
という思いは強くありました。
このような「将来を見据えること」と「そのために必要なことを見定め、挑戦をしていくこと」ができたからこそ、不満を口にせずに済む「今」があります。
中長期的な未来を見据えて行動できるか?
私が起業を水面下で着々と始めたのは新型コロナウイルス感染拡大よりも前のことでした。
今では、在宅ワークなども当たり前になり、Zoomと言えば通じる時代ですが、当時は「Zoom?何それ?」ということの説明から行なっていました。
今振り返っても、その当時から不確実な変化が訪れることを予想し、働き方について向き合っていたかのは大きかったと考えています。(まさか世界中でパンデミックが起こるとは思ってもみませんでしたが…。)
ただ、「未来」を見据えて行動することの重要性を知っていたからこそ、生活が窮地に追い込まれるのを防げたという側面もあります。
実際どんな働き方がいいのかは人それぞれだと思いますが、「未来を見据えてソーシャルワーク実践がしたい」「たった一度きりの人生で社会福祉士として挑戦をしたい」という強い想いをお持ちの方は、これからどんどん「起業」という選択をする人が増えるのではないでしょうか?
社会福祉士が起業する3つのメリット
ではここから社会福祉士が起業する3つのメリットを整理していきます。
- 収入を自分でコントロールできる
- 働く時間を自由にコントロールできる
- やりたいことだけに取り組める
ここから少し詳しく解説をしていきますね。
社会福祉士として起業すれば収入に縛られない
メリットの1つ目は「収入を自分でコントロールできる」ということです。
雇われて働いていると、雇用契約に基づいて時間と労働力を提供し、雇用主から給料をもらいます。
ただ起業したら、「時間給」「月給」とは無縁の世界が待っています。
どれだけのお客さんに対してどれだけの価値を届けられるか?
それがどれだけの対価を得られるかを決めます。
目標とする収入をいくらに設定して、どれくらいの行動をするかは自分で決められるということですね。
- 自宅で副業的に月に5万円稼ぐ
- 100万円以上をひとりで稼ぐ
どちらも現実的な数字です。
あなたが望むライフスタイルに応じて、必要な学びを実践を重ねることで、ひとり起業家として成長を果たし、安定的な収益を構築できることができるようになります。
ただ、実際甘くない現実もあります。
「誰にも価値を届けられない」ということは収入がゼロになります。
学ぶことも実践を継続することもなく「稼げる方法」を考えているのであればそれは甘いと言わざるを得ません。
(この辺りについての詳細は後述の「注意点」でお伝えします。)
社会福祉士として起業すれば時間にとらわれない
次にメリットの2つ目ですが、働く時間を自由にコントロールできます。
1日に8時間以上働くこともできれば、平日の夜の時間や週末に働くことで収入を得ることもできます。
1つ目のメリットで「収入をコントロールできる」とお伝えしましたが、「どれくらいの時間働くか」ということと「どれくらいの収入を目指すか」ということを考えて「どんなビジネスモデルを選択するか?」ということが決まります。
選択するビジネスモデルによっては、「好きな時間帯」に働いて収入を得ることができます。
決められた時間に働きに出ることが難しい方や苦痛な方は自分に理想のライフスタイルにマッチした働き方として起業を考えるのもありかもしれませんね?
社会福祉士として起業すればやりたいことだけに取り組める
メリットの3つ目は「やりたいことだけに取り組める」ということです。
私は雇われて働いているとき「法人の方針」「組織の命令」「上司の指示」に従うのが苦痛と感じる場面がたくさんありました。
これは辞めてから気づいたことですが、私の中で納得できなことに従わざるを得ないことがものすごく大きなストレスになっていたようなんですね。
ただ起業してしまえば、「自分がやりたい」と思ったことをやるだけです。
自分の決断で動くことができる。
当然そこで生じる全ての責任は自分で取るわけですが、それは当然のことと意識して行動しています。
私にとっては「納得できないまま行動させられて、うまくいかなければ責任だけ背負わされる」ということの方が100倍苦痛でしたので、雇われて働くことより起業することの方があっていた気がします。
職場の人間関係で悩みを抱えやしう人にとっては、「やりたいことを選択できる」のは大きなメリットかもしれませんね。
社会福祉士が独立起業するときの注意点
社会福祉士が個人でビジネスを立ち上げるとほかにもたくさんのメリットがある一方で「注意点」もあります。
例えば
「自由度が高い」ということは、その分「責任を背負う範囲が大きい」
ということです。
クライエントに価値を届けることを考えても、自分で責任を背負っていく必要があります。
また、自己管理を徹底しないと健康面や経済面がボロボロになってしまう可能性もありますからね…。
ひとり起業家として経営者の知識とマインドセットを!
また、経営面についても知識を身につけてお金の管理を徹底し、起業する上での責任を背負って行動する必要があります。
起業する前から「なぜ起業したいのか?」ということを自分に問うのは必須です。
その上で、「起業にはどんなリスクがあるのか?」「どうやったら軌道に乗るのか?」ということを最低限情報収集し、リスクをコントロールしながら事業を軌道に乗せていく必要がありますね!
ビジネスモデルについて知識を得ることも大事
私も実際にリスクを極限まで抑えて着々と収益化していく戦略をとったのが功を奏したと考えています。
最初から堅実な方法を選び取り、実行できるかどうかは重要なカギになります。
ただこの情報収集や行動については、「覚悟を決められるか」「学びと実践を重ねられるか」ということに尽きます。
やればできる。やらなければできないということですので、「注意点」もあらかじめしっかり整理して把握し、落とし穴を避けながら前に進む工夫は必要ですね。
社会福祉士が起業したらどうやって稼ぐか?

社会福祉士が起業して収入を得る形態 についてみていきましょう。
一般的には「個人事業主型」と「フリーランス型」の大きく二つに分けることができます。
社会福祉士のひとり起業「個人事業主型」
個人事業主型の収入を得る方法としては、「成年後見人」として活動して報酬を得るとか、専門学校・大学などで講師活動をするなどという方法があります。
ソーシャルワーカーとしての実践力や、講師としての実力を、経済的な価値としてクライエントに提供し、対価を得るということです。
また「介護支援専門員」や「相談支援専門員」として法人格を取得して事業の指定を受け、サービス提供することでも収益を上げることができます。
社会福祉士のひとり起業「フリーランス型」
一方でフリーランス型は「個人として契約関係の中で社会福祉士の専門性を活かして価値提供を行い対価を得る」というイメージでしょうか…。
例えば、医療、教育、福祉・介護の施設で経験や学びなどを活かして、ライターとして記事執筆を受託し、作業をこなすことで対価を得るなどと言った方法もあります。
ただこの「個人事業主型」「フリーランス型」のどちらの働き方をみても、「自分にはハードルが高いのではないか」と思われる方がおられるかもしれませんよね?
そこで私は個人事業主でありながら一般的な方法とは少し違った感覚で収入を得ています。
その内容について最後に少しだけ触れておきます。
社会福祉士として起業して稼ぐための思考
私は「社会福祉士」「ソーシャルワーカー」として現在も社会福祉実践力の向上やまちづくり・地域活動、福祉的課題を抱えた個人からの相談活動なども行っています。
そして、起業家として雇われて働いていたとき以上の収入を安定的に得ています。
ではその秘訣を少しだけご紹介しますね。
実は、『「社会貢献」と「ビジネス」を徹底的に分けて考えている』というところに他の人とは違ったポイントがあるように思います。
社会福祉士の専門性を転用して稼ぐことも可能!
社会福祉士としての知識や専門性、経験値を持っている私たちは、相談スキルや対人援助スキルを「経済的な価値」に変えるための行動に移すこともできるはずです。
例えば「バイスティックの7原則」は、福祉業界では一般的かもしれませんが、他業界では「え、何それ!」という反応が返ってくることも多いです。
でも実際、業務で「相談」を取り入れている会社なども多いですよね?
そんな事業所での研修では「知らなかったです」「めっちゃ役に立ちました」と言われます。
そのほかにも「ラポール」「傾聴」「アセスメント」などは福祉の世界では日常的に使われている言葉であり概念です。
これは語る場所、伝える局面を変えるだけで大きな価値になり、「お金を払ってでも欲しい情報」に変わります。
社会福祉士だからと言って可能性を制限することはない!
また、私たちが福祉に関する国家資格を持っているからといって、何も福祉業界で働かなければならないという制約はありません。
例えば、社会福祉士でも「漁師」をやってもOKですし、「魚屋」をやったらいけないわけでもない!
本が好きなら「本屋さん」をやってもOKですし、複数の仕事をして、週末里親などの形で児童養護施設の子どもたちと楽しい時間を過ごすことだってできるはずです。
つまり、
私たちには無限の働き方・生き方の選択肢がある。
ということを考えた上で、自分の強みや専門性と向き合い、職業選択をしていくこと!
そして、豊かな人生を形にするために、必要なお金を得ることも大事ですよね?
もしその中で、雇われるのではなく自分で起業し、ビジネスを展開して、自由な発想でお客さんに価値を届け、その対価を得ることが必要なら起業すればいい!
そのときに社会福祉士として培った学びやスキルを存分に発揮すればいいだけの話ですよね?
社会福祉士として社会貢献にも本気で取り組む
このビジネスとは直接関係のないところで、
「社会貢献性の高い仕事」
を行うということも大事にしています。
実は最近「社会的起業」や「貢献性の高い活動」をしたいという方からの相談が増えてきています。
詳細はお伝えできませんが、「子ども食堂をやりたいけど資金が集まらない」というお悩みや「助成金や補助金だけではやっていけない」という家庭訪問型の支援事業に取り組まれている方のお悩みを先日を受けしました。
そんなときにお伝えするのは、
「「貢献性の高い事業」と「収益化しやすい事業」をしっかりと分けて考えることが大事ではないでしょうか?」
ということです。
というのも、「貢献性も高く、収益化しやすい事業に取り組む」というのは難易度が高すぎるんですね。
目的を分けて「整理」して考える
そこで、「分けて考える」ということについてお伝えした上で、場合によっては具体的な方法等も伴走型のサポートをして情報提供していきます。
この「社会貢献と収入の確保について整理する」と言うことについて考えてから、いい意味で力を抜いて仕事に取り組み、目の前のクライエントにより高い意識を持って集中してサービス提供ができるようになりました。
私も社会福祉士の資格を取得してすぐは「福祉業界で働かないと」「介護保険法や障害者総合支援法などに基づいて社会福祉士らしい役割を果たさないと」という考え方があって、それが思考の幅を狭めてしまっていました。
今となって思うのは、それらは一つの選択肢に過ぎないということです。
ソーシャルワーク実践は「制度に基づくサービスを活用する」のは大事だと考えています。
ただ、制度やサービスが届かないところでソーシャルワークが求められることが多いとも言えるわけですよね?
そこで私の場合はいろんな紆余曲折を経て、「ソーシャルワーク実践」「福祉実践」は「社会貢献」と位置付けて、家族や自分の生活を安定させるためのお金を稼ぐためには「ビジネス」をしっかりと行うということに取り組んでいるわけです。
対人援助職・コーチ・カウンセラーなどのひとり起業サポート
このような経験や考えのもと、私は「パーソナルコーチ」「ビジネスコンサル」「講師」などでクライエントに価値提供をしています。
特にコンサルとしては、私自身がたくさん失敗を重ねてきた経験を踏まえて、
相談や教育事業などのサービスで自宅にいながら堅実にオンラインで価値提供し、お金を稼ぐ方法
を教えています。
ひとり起業や副業に取り組みたいという方が
経験や実績が全くないところから「ビジネスの基本」について学び、具体的な実践につなげる方法や収益化の仕組みづくりなど
についても教材を作成し提供しています。
さらには「コーチの指導・育成」「福祉現場で働く人や社会貢献生の高い事業に取り組まれる人の相談スキルに関する情報提供」「ひとりでも強みを活かして貢献しながら安定的に収益化するビジネス構築に関するコンサル」「社会福祉士の資格取得のサポート」なども行ってきました。
これらすべてに「社会福祉士として学びと実践を重ねてきたこと」がめちゃくちゃ活きるんですね。
ここまでの内容をまとめると、「社会貢献という位置付けでおこなっている事業では大きな収益化を望まない」ということと、「ビジネスという位置づけで行っている事業はお客さんにしっかり価値を届けて堂々と対価を得る」とういこと。
そして、どちらもこれまで培ってきた学びや経験を活かし、「社会福祉士の専門性」もどんどん活用していく。
これがたった一度きりの人生で「やりたいこと」をやり抜くために大事な考え方であり、働き方だと思っています。
今回は具体的なことはお伝えできませんでしたが、会員限定サイトで詳細をお伝えしていますので、もし興味がある方はそちらをご覧ください。
今回お伝えする内容はここまでとなります。
最後まで読み進めていただき、ありがとうございました。
独自コンテンツ作成
時間や場所を選ばず自宅にいながらひとりでも自分らしさを活かしてクライエント・顧客に貢献する事業を展開したい方へ!
ひとり起業やデジタルコンテンツ作成について基本から学び、リスクを取ることなく小さく事業を開始して長期安定的な事業を展開したい方!
このような方は必見の内容ですので今すぐチェックしてみてください!